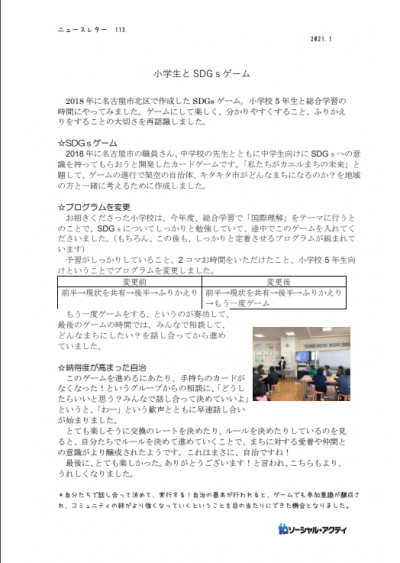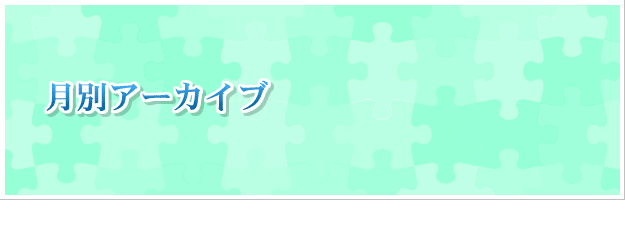
行動を起こすと何かが変わる!
2021-02-28 | ブログ
Actions are more important than words という言葉があります。これを実感しています。
公園を市民が運営していくことを目指して、ルールや運営づくりに反映させていこうと社会実験を行うことになりました。
まだ、企画の途中ですが…
だんだんと煮詰まってきて、関わっている方々の雰囲気がとても前向きになってきました。(ノッてきた!というか、みなさんの本領発揮!を感じます)
そして、チームビルディングができてきたという実感があります。

すると、先日行った本筋のワークショップもコロナ禍の下ですが、積極的に集まってくださり、とても短時間なのに、濃密な話し合いの内容となりました。
(もちろん、社会実験のミーティングもワークショップもオンラインとリアルのハイブリッド!新しい経験や工夫を重ねさせていただきます。)

何か目標をもって、力を合わせて、コトを企画・実施していく!というのは、その場のもつ空気が変わる!ものだなぁと実感しました。
もともと公園に対する想いを持っているみなさんでしたが、社会実験をすることで公園をもっと愛してくれる人を増やしたい、活用してもらいたい。そのためには、どんなことを、誰に働きかけるとよいのか?をより具体的に考えることができました。
公園を中心にしてまちづくりをする、コミュニティをつくっていく、というのは、こういう具体的なことがあると大きな一歩が進みやすいのですね!
社会実験って、そんな意味もあるんだと体感することができました。
そのレポートは後日。お楽しみに。
*おまけ
オンラインとリアルの会議のハイブリッド。イメージ的には参加者がオンライン、ファシリテーターはリアルの場で!なのですが(というか、そのほうが進めやすい)
社会実験のミーティングでは、ファシリテーターがオンライン、リアル参加のほうが多いという…
当初は、結構たいへんでした。
「もう一度、言ってください」「聞こえませんでした」などと言っていたのですが、
集音マイクを使って聞こえやすくしたり
集音マイクには旗を立てて、こちらを向いて話してねをアピールしたり
オンライン参加者を増やしたり…
と、いろいろと工夫しています。
だんだんと双方とも慣れてきて、ハイブリッド会議でもストレスが減ってきました。
ファシリテーターとしても新しく楽しい経験をさせていただいています。
『スマホ脳』気をつけなくては!
2021-02-14 | ブログ
スウェーデンの精神科医 アンデシュ・ハンセン著(久山葉子 訳)の『スマホ脳』を読みました。

(https://www.amazon.co.jp/スマホ脳-新潮新書-アンデシュ・ハンセン/dp/4106108828/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=スマホ脳&qid=1613291798&sr=8-1)
帯に、「スティーブ・ジョブズはわが子になぜiPadを触らせなかったのか?」と書かれておりまして…
とっても気になって入手したのですが、目の前にしばらく置いてあり、なかなか手に取れなかった本でした。
なにが、躊躇させたのでしょうか?
帯には、スマホの影響がずらっと列挙されていて、スマホ漬けになっている私の状況を否定されるのでは?
だとしたら、どうしたらいい?と困惑してしまうのでは?
スマホを忘れて外出すると、不安になってしまう今(テレワークが進んでいる状況では、外出の機会も減ってはいますが…)
さてさて、いかがなりますことか?と。
簡単な内容は
・技術の進化、特にICTの技術の進化の速度に人間の脳がついていっていないことが、現在のさまざまな悩みや精神的な病の遠因なのだということが書かれています。
例えば、うつ病が増えているのは?
狩猟で日々の糧を得ていた頃の名残がまだまだ身体に残っているそうで…

当時、ストレスを感じるのは身を守る手段。
周りには危険がいっぱいなので、脳が感情を使って、危険なことろへ出ていかないようにするというのがストレスと呼ばれるとのこと。
逃げるは〇〇…。でも役に立つですね!逃げてしまえば、とりあえずOK!
でも、その危険信号は強いけれど短期的なもの。
ところが、現代では強くはないけれど、ずっと長期にわたって危険がある。というのが特徴らしい。
人間の脳は長期のストレス用にまだ進化していないので、ストレスにさらされる状態が続き…
本能として逃げ続けることに…
こうやって、危険回避の行動が人類が生き抜いてきた知恵になるのだと。
なので、うつになるのはその人のせいではなく、脳が進化したとおりに動いていることが原因。
となると記されています。
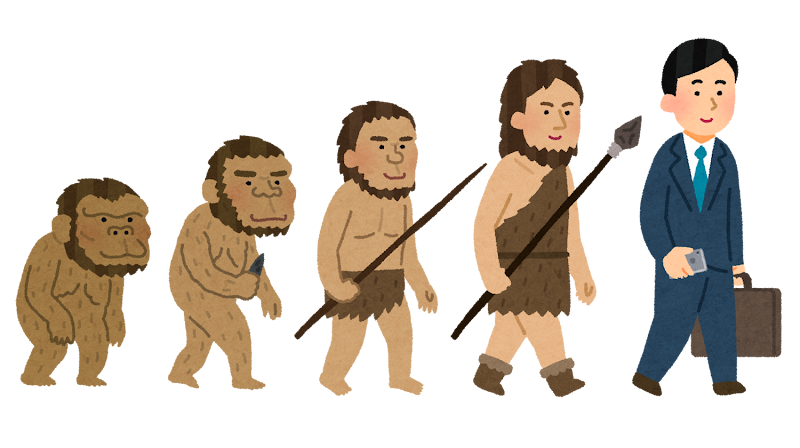
そして、本題。スマホと脳の関係は?
脳はご褒美が大好き。
ご褒美として快楽物質であるドーパミンが分泌されて、うれしくなります。
麻薬を体内に入れるとドーパミンが分泌されるときいたことがあります。
ボランティアをしても勉強をしても、分泌されるとか…
ボランティアや勉強はまず、やることをやるという前提がないとなかなか得られませんが…
スマホと関係するのは…
facebookや tweeterなどで「いいね」がついたり、投稿があったとの通知がくると、「どんな投稿?」と気になってついつい手に取ってみてしまう…
この「いいね」や「通知」によって脳にドーパミンが分泌されるので、快楽を求めて見てしまう。
というループになってしまうそうです。
すると、スマホが気になって何かに集中するということができなくなっていく…

ふりかえってみると
お仕事中も(主に電話はスマホ)電話応対のためにスマホが隣においてあると、プッシュ通知が鳴ると「何なに?」と気になってしまう。
すると集中していたことをいったん止めて、スマホを見てしまう…
集中が途切れて、もう一度、続きに向かって進めるのに時間を要することがよくあります。
この頃、本を読むのになかなか集中できないなぁと感じていたのは、
私だけではだけではなかった…
仲間がたくさんいるようで、ちょっと安心しました。
と言っている場合ではないのですね!
そして、成長過程の子どもたちには、たいへんな影響が出てしまうそうです。
大人はまだスマホのない時代に学業をしてきたので、集中するというベースはできています(よね?)
子どもはこれから、体験して獲得していく過程にあるのに、いきなり気が散ってしまう環境に放り込まれてしまうという、とっても大変なことになっているのだそうです。
ただ、生まれたときからスマホがあれば、付き合い方も分かって大丈夫でしょう?
という見方があります。
これについても、著者は否定しています。
人間の脳の進化のスピードが追い付いていない!ので。
だから「スティーブ・ジョブズは、わが子にiPadを触らせなかった」のですね。
大人であっても、集中力が減退していると感じるのであれば、スマホは隣の部屋に置いたりして、デジタルデトックスを心掛けることも大切なのだと思いました。
スマホで目覚まし→目覚まし時計に戻す
スマホで時間を確認する→時計を見る
など、スマホに頼っていた機能を元に戻すことも対策だと記載してありました。

そして、何より、体を動かすことに大きな効果があるとのことです。
1日20分くらいで良く、ウォーキング程度でOK!(それ以上やっても効果は変わらないとのこと)
かる~く身体を動かすことを決意しました!
*生活環境を見直す視点の一つだと思いました。
ニュースレター第113号「小学生とSDGsゲーム」
2021-02-03 | ニュースレター
迫ってくる2030年。
SDGsのゴール達成の年です。
いろいろなツールを使ってSDGsを推進しようという動きがあります。
SDGsという言葉を見ない日はないくらいと言っても過言ではないかも。
2年前に中学生向けに作成した手づくりのカードゲーム。
今回は小学校5年生向けに少しアレンジして行いました。
ゲームの力で積極的に参加してくれて、自分たちのまちが話し合いと合意で形を変えていくことを体感してくれたようです。
また、自治にについても体感してしてくれたのでは?
小学生パワーにへとへとになりながら、楽しい時間を過ごしました。
ニュースレター第113号「小学生とSDGsゲーム」ご覧くださいませ。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370