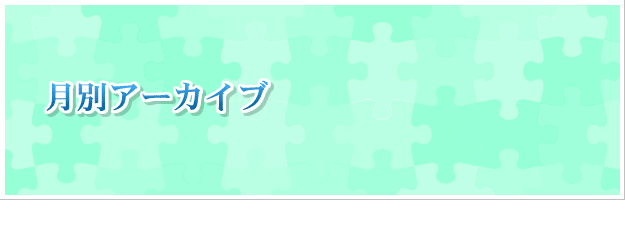
ファシリテーション・サミット2023無事終了しました
2023-06-23 | ブログ
NPO法人日本ファシリテーション協会では、毎年、総会の前に2日間かけてイベントをしています。
場所はFAJの拠点を順に持ち回りしていました。
コロナ禍で2020年はお休みしてしまいましたが、その後は2021年はオンラインのみ、2022年からハイブリッドで開催してきました。

今年は、名古屋で行うことになり、昨年の8月あたりから会場探しをはじめ、毎週1回のミーティングを行ってきました。
コロナ禍以前は、全国規模のミーティングはオンライン、地域でのミーティングはリアルで会って行っていました。
オンラインでのミーティングのスキルもあがってきたこの頃は、オンラインでミーティング。
現場確認等だけはリアル!となってきました。
(オンラインのミーティングは、移動しなくてよいし会場を確保しなくてよいので、便利!)
さて、その全国イベント「ファシリテーション・サミット2023名古屋」では、
・基調講演(ハイブリッド)
・ワークショップ・レクション1(リアルとオンライン)
・ポスターセッション(リアルとオンライン)
・ワークショップ・セレクション2(リアルとオンライン)
・サミット宣言(リアルと配信)
というプログラムでした。
このプログラムの中で、ワークショップ・セレクション1,2のうち一つずつ担当しました。
先端の技術と、人間のベーシックなよりどころ。ベースを自覚して、技術を積み上げる!というストーリーだ!と一人で喜んでいました。
1つは、「ChatGPTと話し合いの見える化システムを使って、ファシリテータ―のトレーニングをしてみよう!」
というものです。
もう一つは、「つなづいても自分の足で歩こう。挑戦とつながりを信じて」です。
こちらのワークショップは、心に沁みて、まだ言語化できない状態です。
でも「人がつながる」って本当に必要なこと!というのが、すうっと心に入ってきました。
さて、
ChatGPTの方は、名古屋工業大学の白松先生と(株)ハイラブルの水本社長にお越しいただきました。
ChatGPTにあらかじめキャラクターを設定して、話し合いを行ってもらう。
そこに、ファシリテーターはどのように介入するのか?を話し合って入力します。
あとから、そのときの話し合いをふりかえるのに、見える化システムを見て、ふりかえる
ChatGPTの使い方と見える化の体験をしていただきました。
反応は、もちろん!
とってもお楽しみいただけたようでした。
このWS、企画の段階からワクワクしていました。
昨年、ChatGPTが無料でリリースされる前に、名古屋工業大学の先生をお招きして行った定例会とは、少し異なった使い方ができました。
工夫次第でいろいろな活用ができるのだなぁと思いました。
昨年の定例会の時よりもぐっと進んだChatGPT。
これから、どこまで行くんだろう?(想像できません💦)
とりあえず、経験してみることも大事なことだと思って、チャレンジしてみました。
ファシリテーターの代わりをAIができるか?問題があります。
今までは、資料をさっと出してくれたり、根拠を調べてくれたり、人間ファシリテーターが言いにくいことをズバッと言ってくれたり…
AIとうまく付き合っていけば、ファシリテータ―のサポートができるよね。
という話をました。

ところで、いつ、AIがファシリテータ―の代わりができてしまうのでしょう?
ここ10年ほどで、ドッグイヤーを超える速さで進んでいるAI。
AIに人間の感情は分からないよね。
なんて思っていては・・・
感情が分析できるのであれば、組み立てる事もできそうな気がします。
AIの進化が楽しみでもあり、人間の領域に迫られる…複雑です。
これからも、白松先生に教えていただきながら、なんとか時代についていこう!と思ったサミットでした。
もっと、楽しいことになりそうです。
ファシリテーションの基礎には「共感」
2023-06-13 | ブログ
FAJ(日本ファシリテーション協会)の第72号のニューズレターが届きました。
(これは、会員しか読めないのですが…)
今、FAJの中の広報委員会におり、ニューズレターの記事を書いています。
インタビューの記事は、論文とは異なる書き方なので、始めは戸惑いましたが、少しずつ慣れてきました。

今号では、NPOであるFAJは今年、20周年を迎えます。そして、FAJのミッションの一つが「ファシリテーションを普及すること」です。
どのくらい普及したのか?についての調査とともに、
FAJの会員ではないけれど、ファシリテーションの必要性を感じてくださっているお二人にインタビューしました。
その中のお一人。大学の先生へのインタビューで、腑に落ちたことがありました。
それは、ファシリテーションの基礎には「共感」があることでした。
その先生は、野生哺乳類の生態についてご研究されています。
インタビューの中で、印象に残ったのは、
・野生哺乳類の生態を研究するには、野生哺乳類の気持ちによる添うことが大切!
・野生哺乳類は、町を跨ぎ、市町村を跨ぎ、県も跨いで行動する。そのために野生動物の管理計画には、さまざまな調整が必要!
とのことでした。

野生動物と人間の関係性にもファシリテーションが求められることを知りました。
動物の気持ちに寄り添う…共感がないとできませんよね。
もちろん、ここでの共感は、「エンパシー」
そして、学生へのメッセージをお願いしたところ
「人間は社会的な動物で人と関わらないと生きていけない」
「対人間だけでなく、対動物にも想像することが基本です」
「自分を知って、自分だったらどうする?から出発して考えます」
「これには、ファシリテ-ションのスキルがに役立ちます」
といういくつかのフレーズです。
共感の方法と、共感することはファシリテーションの基礎なのだ!ということを生態学の先生からも教えていただきました。
そういえば…
ワークショップや会議などの話し合いの中で、
この方は、このグループは今、
どんなことを考えているんだろう?
何を感じているんだろう?
と想像しながら話し合いを進めてきます。

共感して、進め方を考えていくのです。
ファシリテーターが関わるプロセスには タスクプロセスとメインテナンスプロセスがあるという説があります。
タスクプロセスは、文字通り話し合いの目的に向かって進むプロセスです。
メインテナンスプロセスは、感情面のプロセスです。
表面上はうまくいっているようでも、いざという段階でひっくり返るということがあるとすると
そのときは、感情面がうまくいっていなかった…
ということ、なくはないですよね。
そこに、共感が必要なのかもしれません。
共感・エンパシーここを鍛えることができる方法を模索してみようと思いました。
ニュースレター第141号「アイデア会議のファシリテーター」
2023-06-02 | ニュースレター
子育て支援の一般社団法人こどもと暮らすiiねっとが設置、運営している「HATSUMEI堂」という施設があります。
ファブラボって聞いたことありますか?
DIYなどの専用の機械が置いてあり、料金を支払って使わせてもらえるという場です。
この頃、人気のファブラボです。
子どもの創造力を伸ばしたい。思いっきり好奇心をみたすものづくりをしてほしい。
という想いでつくられました。
この想いを、どうやって実現させるか?
どうやって知ってうか?
などのアイデア会議のファシリテーターをしています。
アツイ想いを持った人が集まる場のファシリテーション。
楽しいけれど、なかなか思うようにいかないことも…
でも、参加している人たちの気持ちはひとつ。
子どもたちの笑顔のために、楽しく進んでいます。
ニュースレター第141号「アイデア会議のファシリテーター」御覧ください。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370




