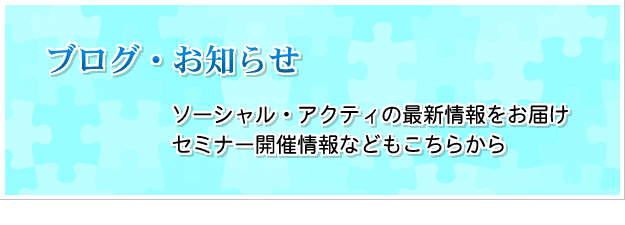
今期の大学授業のふりかえりを
2025-01-29 | ブログ
半期ごとの授業が1つ、終わりました。
今期心がけたことを中心にふりかえってみたいと思います。
お伝えしたいことは大きく2つ
言語化を体験する、ふりかえりのまとめ
です。
授業は、拙著『多様な市民とつくる合意~コミュニケーションのファシリテーションのレシピ~』です。
 (アマゾンより https://x.gd/ZvxD2)
(アマゾンより https://x.gd/ZvxD2)
1.言語化を体験する
これは、以前のブログ『「好き」を言語化する技術』を読んで、でもお伝えしたように、まずまず成功!かと。
ふふりかえりシートに感想や気づきなどをワーク毎に記入してもらっています。
ふりかえりシートを読むのが楽しくなりました。
(ひとこと、「楽しかった」だけでは、寂しすぎます。この記入が多いことから、言語化するということに興味をもったのでした。)
最後の授業のふりかえりシートには、「気持ちを使える経験ができました」という記載もあり、伝わったんだ!とうれしくなりました。)
 (アマゾンより https://x.gd/Kw4IL)
(アマゾンより https://x.gd/Kw4IL)
2.ふりかえりのまとめ
毎回、書いてもらっているふりかえりシートですが、最後の回は、半期分まとめたふりかえりもしてもらっています。
・授業の中で、一番印象に残ったことは?
・今、使っている、使ってみたいスキルは何ですか?
の2点です。
この項目が、毎年気になります。
ここを見て、次に活用できれば!と思っています。
・授業の中で、一番印象に残ったことは?
今までやってきたなかでは、一番多いのが「ブラインドワーク」でした。
以前は、授業2回使って、テーブル上でのワークと、体育館で身体を使ったワークをしていました。
(授業の内容を見直す時に、テーブルワークのみとすることにしました。)
そのときは、もちろん!身体を使って動くので、ダントツの一番でした。
でも、目隠しをして、普段意識していない5感のうちの視覚以外の4つの感覚を研ぎ澄まし、コミュニケーションをとる!というのは、新鮮な体験のようです。
しかも、目隠しして2人一組で鶴を折る。一人が目隠しをし、もう一人が折り方を言葉だけで教えるのです。このときは頭フル回転のようです。
鶴の折り方を知らない相手に、何気なく折っていた(意識せずに、手が勝手に完成させるイメージ)ことを言語化して伝える。
しかも、相手は目隠しをしているので、うまく伝わらない…
とってもじれったい思いをします。
(学生の間を見て回っているときに、少し手助けしようと思っても、なかなかうまく言語化できません)
次に多かったのが「傾聴」と「共通点さがし」でした。
傾聴のワークでは、まずは、否定せずに話を聴く練習「Yes And」をしています。
相手が話をしたら、「そうだね」と言い受け止める。次に「さらに」を付け加えることをしています。
否定されないということが予め分かっていると、安心して話すことができるという感想が書かれています。
(失敗したくない、否定されたくないという気もちが大きいのでは?と思います)
「共通点さがし」は、アイスブレイクで使っています。
席を立って、積極的に動いて、話したことがない人、あまり話していない人のところへ行って、共通点を探す
というものです。
(このときに話した人と友だちになったという声をよく聞きます。やって良かった!と思えます。)
このスキルをアルバイトのときにも活用しているとのこと。
内容を読んでいると、どうやって話しかけたらいいのか?何を話したらいいのか?が分かった!というコメントが多くありました。
確かに、大学に入ると、人間関係はガラッと変わりますから、初めての人ばかり。
たぶん、こんなに環境が変わるのは、初めての経験でしょうから、友達のつくりかたを知るのは、とてもうれしいことなのだろうなぁと、改めて思いました。
後は、リフレーミング、自分チラシ(前段階としてSWOT分析やジョハリの窓のワークをします)も多く印象に残ったようです。
(リフレーミングは、平日夜のオンライン定例会で取り上げたテーマですが、大人相手でも好評でした。年齢は関係ないかもしれません)
今後も、学生のみんなと楽しみながら、コミュニケーション、ファシリテーションを体験し、学んでいきたいと思っています。
もちろん、大人とも!
学会誌に掲載されました(査読付き)
2025-01-15 | お知らせ
日本地方自治研究学会の学会誌「地方自治研究Vol.39 No,2」に査読付き論文が掲載されました。
タイトルは
「租税教室を活用した自治意識の萌芽形成の試み」です。
内容は
美濃加茂市で6年ほど携わられていただいた小学校6年生むけの租税教室。
ここで、租税境教育は主権者教育、自治意識の形成に寄与するのでは?というテーマを掲げ、実践し検証しました。
内容は、読めませんが、バックナンバーのお知らせを!
https://www.skattsei.co.jp/tihoujichi/
美濃加茂市さん、はじめ、みなさまのご協力で書き上げることができました。
ありがとうございました。
自分の気持ちを言語化するには「推し」から?
2025-01-15 | ブログ
『「好き」を言語化する技術』という本を見つけました。
「言語化」するには?を密やかなテーマにしてきたので、「これはステキな出会い!ここで大きく区切りがつくか?」と期待して読みました。
 (アマゾン https://x.gd/srYdl より)
(アマゾン https://x.gd/srYdl より)
なぜ言語化?
なぜ、言語化?と言いますと、
大学の講義の後で「ふりかえりシート」を学生さんに書いてもらっています。
人によって、書く量に差がありすぎて…
自分の気持ちをたっくさん書いてくれる人は2割くらい。(とても読み甲斐があり、うれしいです)
一言で終わってしまう人も1割くらいいました。(2行は書いてねっていったのに…)
ということがあります。
『他者の靴を履く』で読んだ衝撃的なフレーズがあります。
「自分の気持ちを言語化できないと、心がスッキリせずにモヤモヤ。いつのまにかストレスがたまり、うっぷんになり、暴力として出てしまう」というものでした。
『ケーキの切れない非行少年たち』でも、同様のことが書かれていました。
自分の気持ちをちゃんと言語化する!というのは、とても大切なことだったのです。
もちろん、学生さんたちがそうなるということではないです。
ただ、将来、社会に出たときに、とても苦労するのでは?と思ってしまいます。
私は、若い頃、会社での人間関係がうまくいかず、ストレスをためたなぁという経験がりまして…
しなくても良い苦労はしない方がいいかと…。そして、自分の感情を言語化することで、ストレスが減るのであれば!
と思い、ふりかえりシートを活用して、言語化することを身に着けてほしいなぁと思ったのです。
今期の授業では
ふりかえりシートに、丁寧に問いを書くことにしました。
例えば、ワークの後に感想を書いてもらうところで、今までは「やってみた感想は?」のようなフランクな書き方をしていました。
すると「楽しかった」「面白かった」で終わってしまう…(それは、そうですよね。聞かれたことに答えるという高校までのテストの回答と同じであれば)
でも、これでは2行になりません。
きっと学生は、「聞かれたことには、答えた!それ以上、何が聞きたいの?」と思っていたのではないか
これ以上、何を書けと?思ったのでは?と想像します。
これは、聞き方が悪かった、と反省しました。
そこで、気持ち・感想を言語化するには、どうしたら良いのか?質問者の私が求めているのはどのようなことなのか?を細かくして聞いたみよう!と取組みました。
以前、このブログでご紹介したVチューバ―かなえ先生の分かりやすい言語化のテクニックを使って、ふりかえりシートに書き込んでみました。
例えば、「ワークをしているとき、どのような気もちでしたか?それは、何があったからですか?なぜ、それがあったらそのような気もちになったのでしょうか?」というように。
とってもくどい質問で、書いている本人も「ちょっとねぇ…。」と思いつつ取り組んでみました。
結果は、一言「楽しかった」と書く学生が激減!
一つ一つの質問に答える形で書いてくれました。
もちろん、それでも一言で終わらせる学生もいます(笑)でも、今では、ほんの数人!
今まで、何を書いたらいいのか?が分からなかったんだなぁと思い、質問者としての自分を顧みたのでした。
そこへ「推し」「技術」というワード
前置きが長かったのですが、「推し」「技術」という即効性のありそうなワードが飛び込んできたのです。
これは、もう、読むしかない!ですよね。
読んでみると…
たぶん、「自分の気持ちを大切にする」ためのきっかけとして「推し」の魅力を伝えるという場面を設定して解説してあるのでは?と思いました。
「推し」っていう言葉はとっても魅力があります。
読んでみると、共通点がたくさんありました。というか、技術としてはほぼ、今までやってみたことと同様ですが、その奥のマインドがステキでした。
「推し」を推す気持ちの深さに脱帽です(笑)
同じ技術とは…
スキルとしては、
「推し」の「自分の気持ち」はどう思ったのか?
どう思ったかは、文章や行動の何が、そう思う気持ちの元なのか?
そして、その「何」がどうして、そう思うようにさせたのか?
を書くというものでした。
その前提として、「どう思った」「何」を細分化して保存(メモなど)しておくことがオススメ!
たくさん保存することで、自分の「推し」への気持ちが強くなっていったり、推しが残念なことになっても傷つかなかったりとか。
そして、素敵なマインドは、
「推し」を語ることは、「自分の人生」を語ること
というものでした。
自分の「好き♡」がたくさん保存されて、その基礎にあるものを眺めると、自分の人生が見えてくる!
前向きでステキな考え方!と思いました。
伝えるにも、ワクワクと楽しそうです。
授業にも、この考え方で取り入れてみよう!
来年度の授業では、この考え方を伝えて、一度、みんなで書き方のワークをしてみよう!と考えています。
さて、楽しんで取り組んでくれるかな?
どんな反応が来るか?今から楽しみです。
ファシリテーションでも
研修などでも、ファシリテーションをする場面があります。
そのときにも、活用できそうです。
前向きで深いふりかえりから、次のステップが見えてくることは、たくさんあります。
楽しく、有意義な場になりますように!
みらいラボ名古屋に参加しました
2024-12-31 | ブログ
人工知能学会の中の市民協創知研究会(通称:みらいラボ〇〇)という研究会があります。
https://sigcci.github.io/sigcci/
目的は、
「研究会開催地域のコミュニティに積極的に働きかけ,中高生や高齢者を含む市民と研究者との共創を試行する場を提供し, 学術研究として広く国内外に発信する場を提供する.さらに,地域横断的あるいは組織横断的に方法論を共有し横展開する等の取り組みや, 地域や組織を超えたより大きな集合知に繋がる協働・共創の取り組みを目指す.」
となっています。
人工知能が市民の生活のどこに、どんなふうに役立つのか?についてフィールドを設けて研究してみるというものです。
第3回のなごやで、未来茶輪について発表して、ベストプラクティス賞をいただきました。
https://sigcci.github.io/sigcci/conf3/index.html
さて、開催当初から現場とオンラインのハイブリッドで行われています、この研究会(さすが!IT関係のみなさま)。
体調が不良でも、現地が遠くても参加できます。
今回は、せっかくの名名古屋開催なのに、体調不良のためオンライン参加となってしまいました。
オンラインでも発表は、楽しく参加することができました。

↑今回の開催場所は、中川運河沿いにできた「にぎわい交流拠点:パレット」でした。
大学院生さんたちが主に発表してくださったのですが…
自然言語処理関係の方が多くて…
ファシリテーションの視点からみても、とても興味深いものが多くありました。
・会議が停滞すると問題提起してくれるとか
・この意見は賛成・反対だと判断してくれるとか
こんな機能があったら、会議ファシリテーションもラクになりそうな機能いろいろでした。
自然言語処理での言葉の流れとの違い(今後の課題です)
いままで、日本ファシリテーション協会(略してFAJ)で学んできたファシリテーションの捉え方と異なる捉え方が多々あり!
(すみません、ここは、今後、もっと明確にお伝えできるようにしなくては!と考えています)
戸惑ったり、メモしたり…
新しいことを学べる場になっています。
成田祐輔さんの『22世紀の民主主義』では、人が考えていることを勝手にAIが抽出して、政策をつくってしまう!という将来像が示されています。
ファシリテータ―としては、仕事がなくなってしまう?(笑)
という話ではなく…
人が本音で考えている事と、人に伝えるときの言葉は違うものだと捉えています。
全員が本音を言えば、世の中が良くなるとは限りませんよね。
(建て前(あるべき姿)を語ることで理想の社会を目指していけるということが根底にあります。)

余談ですが、NHKのドラマで「17歳の帝国」というのがありました。
https://www.nhk.jp/p/ts/VNXRGXV8Q3/
これは実験都市で、全国から選出された人が(なぜか20歳前後の若者)選出され、そこに住む人たちの考えていること(膨大なデータ!)をAIがまとめて政策にしてくれる…というような内容だったと記憶しています。
これが真の民主主義だ!とばかりに
そこで生まれる矛盾にどう対応するのか?みたいなことを描いていました。
何を大切にして、何を活かしていくのか?という選択がカギになるのかもしれません。
余談に走りすぎてしまいました💦
自然言語処理、ビッグデータの活用といっても、やはりベクトルをどこに合わせるのか?
修正可能か?
それはどの時点なのか?
修正するに際してのベクトル・方向性をどこにもっていくのか?
その決め方は?
などなど…
考えておきたいことは、たくさんあるのだと思いました。
その中で、
人と人が話す時のファシリテーション(リアルとオンライン、時差もあり)
人とAIが対話するときのファシリテーション
AIとAIが対話するときに人はどのように介入するのか?
など
ファシリテーションの仕方、にも新しい分野が生まれることになりそうです。
2024年もお付き合いいただき、ありがとうございました。
みなさまに幸せな一年が訪れることをお祈りしつつ…
良いお歳をくださいませ。
鞆の浦に行ってきました
2024-12-18 | ブログ
広島県福山市にある鞆地区(鞆の浦)に行ってきました。
(福山市は弊社のある愛知県岡崎市の親善都市です)
鞆の浦の景観
20年以上前に一度、旅の途中で車で立ち寄ったことがあるだけでしたが、
鞆の浦の架橋計画が住民の反対で断念されたというのはその後、聞きました。
その経緯は…
この地図のように鞆港を埋め立て、生活のための橋を架けようというものでした。
(地図、経緯ともにhttps://www.jawan.jp/rept/rp2020-j131/2.html)
道幅の狭い鞆地区。下水のためや、渋滞解消のためなどの理由で、この計画が持ち上がったそうです。
しかし、住民への説明も不十分でこの計画が進み、明らかになったのは1983年のこと。
景観を破壊するこの計画は、生活を優先する住民との分断を生んでしまった。
2009年10月に架橋取り消しを求める住民訴訟で、広島地裁は計画取消しを命令する判決が下った。
そして、広島地裁はこの判決で、
「鞆の浦の歴史的景観を享受する利益は法的に保護するに値する」「鞆の浦の景観は瀬戸内海の美的景観を構成し、文化的歴史的価値を有する景観として国民の財産ともいうべき公益」
と判断した。
とのこと。
公益に値する鞆の浦の景観。
それを体感してこよう!という目的でした。
リッチなまちだった鞆の浦
福山駅からバスで30分ほど揺られて到着。
瀬戸内海に浮かぶ島々とともに、入り組んだ海岸線。
そこに入り組んだ道があり、街並みもほぼほぼ保存されていました。
(日本遺産、重要伝統的建築物保存地区にもなっていました)
まちあるきがとっても楽しい地域でした。
朝鮮通信使の寄港地であったため異国情緒のあるお寺からは、交易が盛んだったことがうかがわれます。
潮待ちという地域で「瀬戸内海に突き出た沼隈半島の東南端に位置する鞆の浦。東は紀伊水道から、西は豊後水道からの満ち潮が沖合でぶつかるため、船はその潮に乗って鞆の港へ入り、引き潮に乗って再び船出します」とのこと。
重要な港だったのですね~https://visittomonoura.com/history/

沼名前(ぬまくま)神社
ちょっと異国っぽい
そして、保命酒というのが有名だそうで、4軒も保命酒をつくっている造り酒屋がありました。
お店によって、味は異なるそうですが、16種の薬草をみりんに溶け込ませたお酒です。
これを江戸時代後半に福山藩の当主だった中村家が専売として、類似品が出回ることを阻止したとのことです。
そして、ペリーやハリスが交渉の場で飲んだというお酒がこの「保命酒」だったそうです。
https://www.kigusuri.com/kampo/furusato/tomo.html
↑の情報もありますが、保命酒のお店でも教えていただきました。
試飲もさせていただけます。
みなさん、鞆の浦にまつわるいろいろなことを親切に教えてくださいました。
甘くて漢方の香りがして、美味しいもので、漢方が苦手という方でも、飲めるかも!
一緒に行った友人もこれなら飲めると言っていました。
鞆の浦名物?
以前行ったときの写真がないのですが、
急こう配の坂の上から見たときに、ちょっとしたスペースで(たぶん)魚の行商(と、後で教えてもらいました)をする方が、スタンドのようなお店を広げて、そこで魚をさばいていたのが印象的でした。
今回、さすがにその景色にはお目にかかれなかったのですが、
海沿いで魚を干している珍しい景色をみました。
どうやら、場所が決まっているようで、(多分)さよりの干物を干していました。
勝手に、これは鞆の浦名物!と決めています(笑)
お寺や神社も多くあり、まちあるきが楽しい鞆の浦でした。
もちろん、魚も美味しくて…(刺身といえば、鯛だそうです。さすが瀬戸内!)
目にもお口にも、うれしい場所でした。
ジブリのポニョの舞台だそうです。
(ポニョ、見たことないので、今度見てみなくちゃ!)

まちかどに、ポニョの噴水が!かわいい


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370




