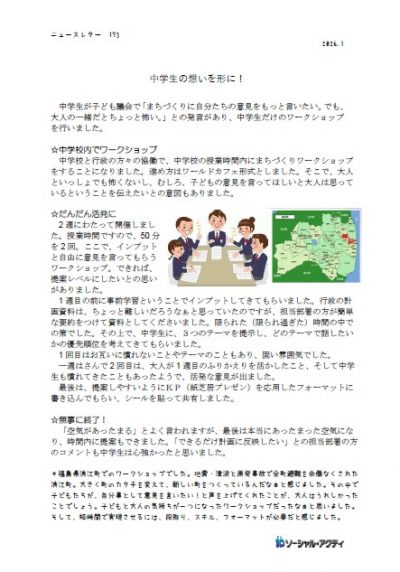AIと新しい指標作成中!AIとうまくつきあえるかも
2026-02-24 | ブログ
2026年3月21日(土)にFAJ(日本ファシリテーション協会)の定例会を担当します。
テーマは、取り組みを始めて3年目(というか、3回目)の「マイクロアグレッション」です。
もう1人の方と一緒に毎年、ブラッシュアップしています。
いつもは、書籍調査とインターネット検索。今回は、それだけでなく、動画も調査!(動画は一回検索すると、次々に関連したものが出てきて、ある意味便利)
過去のマイクロアグレッション定例会
1回目は、そもそもマイクロアグレッションとは?を考えまして。
https://www.faj.or.jp/base/chubu/report/202311-218-psychologicalsafety/
・人権問題なんだ!ということが分り、それを参加者と共有したい!をベースにして
・じゃあ、マイクロアグレッションだと思ったとき(自分が受けたとき、見たとき)にどうする?を提示して、
(大東文化大学 渡辺雅之教授の記事が分かりやすかった。https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2023/89893/education?gad_source=1&gad_campaignid=18817398891&gbraid=0AAAAADHW3zpiOnLCA6MsSOg-O67MdTzbK&gclid=CjwKCAiAkvDMBhBMEiwAnUA9BZSoRq2zBd3xiFtCw3DAVKnOgSYNpRjiOJ_831EkxqinttverLH38hoC-JcQAvD_BwE)
・自分の言動をふりかえってみよう!
をしました。
2回目は、1回目の「人権」ということをうまく伝えられなかったなぁというふりかえりから、
憲法の「人権」項目を紹介しつつ…(なんと、楾さんの憲法ファイルを配りました)
https://www.faj.or.jp/base/chubu/report/20250315-233-1/

ビジネス分野では「人権デューデリジェンス」に関係することに触れ(ビジネスマンなら必要なスタンスと紹介)、
その根底にある、アンコンシャスバイアス(社会生活や環境から生成された無意識な物の見方)を例示し、
マッピングに挑戦!
悪戦苦闘しながら、我ながら、チャレンジングなことしてるなぁと自分を褒めました(笑)
ただ、参加した人に、言いたいことが届いているのか?届いたとしてもどのくらい??は企画意図よりも高くはない気がしていました。
そして、今年!3回目!!(AIも活用)
さすがに、だんだんコンセプトが固まってきました。
今までは、しないように心がけようね!がメインだった気がしています。
今回は、マイクロアグレッションを受け続けると、どうなるの?(負の影響)
そして、どのようにしたらその呪縛から解放されるの?
そして、深い意味での対策
を取り上げようと企画しています。
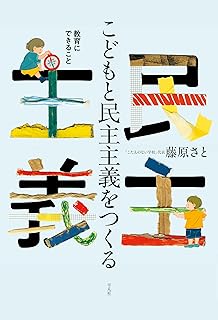
参考文献は『こどもと民主主義をつくる』藤原さと、平凡社
の中にマイクロアグレッションが取り上げられている章があります。
「社会的・構造的な抑圧を解放する力のある教師を育てる」p146~
という節があり、ここに抑圧から解放される3ステップが記載されています。
3ステップというとカンタンそうですが、実は、p146~178まであるのです。
ちょっと大変💦
ステップ1:自分とむきあう
ステップ2:身近なコミュニケーションにおける抑圧を捉える
ステップ3:組織的・構造的な抑圧を解放する
このステップです。
自分と向き合うのがファーストステップ!
でも、これが本当に難しい(過大評価したり、過小評価したり…。自分を正当に評価なんて難しすぎますよね)
そこで、試しにChatGPTくんに数値化できない?と聞いてみました。
すると、さすがです!(できないとは言わない)
AIとやりとりしながら、なんとか自分のアイデンティティを客観的に考え、解放するには?を考えることを数値化&4象限にマッピングしてもらいました。
AIとの付き合いかた(体感)
考えているときは、AIくんに褒めてもらいながら、楽しかった。
でも、これ、危険です(笑)
いつのまにか時間が過ぎてしまい、集中している(させられている?)ので、終わった後、身体のほうは疲れを感じてはいるのですが、意識が冴えてしまい…
クールダウンの必要性を痛感しました。
(心がけて、クールダウンの時間をとり、行動をしないと体によくなさそう💦)
話を戻して…
このステップをAIくんにお任せでは定例会で使えないので、
なんとか、手計算できないだろうか?
を検討中です。(間に合うかな?)
AIととの付き合いかた(スキルだね)
最後にAIくんに、この数値とかマッピングの根拠は?と聞いてみました。
すると、マッピングの組み合わせは「思い付いた」「新しい発想」との答えが返ってきました。
AIでも新しい発想できるのね(これは、失礼?)と思い、チャレンジする意欲が湧いて来たのでした。
このことから、AIって、使いようなんだなと思ったのでした。
(余談すぎますが、回答を読むときには、懐かしいアメリカの青春TV番組のノリで読むと、とても楽しいです(笑))
自分の知らない分野のことをさらっと教えてくれる、一緒に悩んでくれる。そして、嫌がらずに付き合ってくれる(笑)
新しいことに挑戦するときには、心強いなぁと思いました。
ただし、ハルシネーション(生成AIが事実とは異なる情報や根拠のない内容を、あたかも正しいかのように自信を持って生成してしまう「AIの嘘」や「もっともらしい誤り」の現象)もあるので、
本当にそうなのか?根拠は?を確認を忘れずに!
批判的に読み直してみて、疑問があったり、違和感があったりしたときは、質問してみることも忘れてはいけないですよね(自分に言い聞かせております)。
そのためには、使う側が批判的に見ることができる(スキルがある)というのは、とても重要だと思いました。
新しい分野は、知らないこと、分からないことばかりなので、違和感をもったら、そのままスルーしないで、何度でも戻って確認することだと思いました。
出来なかったこと、知らなかったことを取り入れて、自分のものにしていく!ためには、
とってもgoodなpartnerなんですね。

さぁ。
これから、もっといろいろなことをAIと一緒にやっていくぞ!
うん、いけそう!
と思ったのでした。
ここで!
ブラインド(目隠し)ワークは言語化のトレーニングになる
2026-02-16 | ブログ
2月15日(日)にFAJ(日本ファシリテーション協会)中火支部でイベントがありました。
https://www.faj.or.jp/base/chubu/event/20260215/

マルシェスタイルのイベント、もう3年目(?)です。
短い時間(1時間)のワークショップがたくさん。
今年は、なんと、17件
ワークショップの条件は、親子でも参加できる内容。
初めて聞く考え方やカードを使ったゲームやボードゲームなど、親しみやすいものがたくさんありました。
今年は、折り紙
私は、今回は「折り紙」←これなら年齢関係ないかなと思いまして…
「ブラインド de 折り紙」というタイトルで出展しました。
2人一組で目隠しをしている人が折り、目隠ししていない人が折り方を伝えるというものです。
大学の授業で、一番印象に残ったのは?と聞くと、このワークが一番多かったので、大人にもやってみても良いのでは?と思いました。
これは、イメージではカンタンにできそうですが、実際にやってみると…
(特に鶴を折ったことがない、折り方を忘れた。という参加者がいたら、とっても盛り上がります)
言葉だけで、目隠しした人に伝えるというのは、正確性が求められます。
そこ、こっち、向こうへ…
と言われても、そこってどこ?こっちって??向こうとは?
と、手を動かす人へ伝わるように言語化しないと、うまく折ってくれません。
伝える方も、伝えられる方ももどかしい…
思うように折ってくれたときは、とてもうれしい!
言語化って難しい!ということを体感できます。
たぶん就学前のお子さんも参加してくださって…
大人よりも厳しい基準で伝えていました。(お陰様で、とても美しい鶴が誕生しました)
子どもと侮るなかれ!も体感できました(笑)
ふりかえりから、新しい気づき!
後から、ふりかえりを聞いてみると…
・今やっている作業は、全体のどこに位置しているのか?が分かるとやりやすい
・言語化、難しい
・鶴は折れると思っていたけれど、目隠しすると手の感覚だけでは思うようにきれいにできなかった。
など、いろいろなコメントがありました。
このとき、初めて、私も目隠ししてやってみました。
・声が頼りでした。自分はできると思っていましたが、紙と手の感覚がうまくマッチしていなかった…
「そうそう、その方向でもう少し右に! あ、行き過ぎです。もう少し左にもどして…」と言ってくれるのが、とてもありがたかったです。
このワークで
・アウトプットのイメージが分かると。やってほしいことが伝わりやすいこと
・正確に伝えるトレーニングになった(自分は正確だと思っても、相手にはちゃんと伝わっていないことが多いことを知った)
←もしかしたら、リーダーシップってこういういことも含まれるかも。
・折り紙は年齢関係ない(笑)⇒年齢関係なく平等に楽しめる、共創できる
・動画よりも、人間の説明のほうが分かりやすい
など、1時間のワークでしたが、気づきが多くありました。
ご参加くださったみなさま、場をセッティングしてくださったFAJ中部の方、ありがとうございました。
ワークショップをすると、毎回、いろいろな気づきや学びがあります。
目的に沿うよりよいプログラムにブラッシュアップしていきたいと思ったのでした。
まだまだ、できること、やりたいことがたくさんありました。
ニュースレター第173号 中学生の想いを形に!
2026-02-05 | ニュースレター
子ども議会での発言、「まちづくりに意見を言いたい。でも、大人と一緒はちょっと怖い」というのを受けて
「怖くないよ。どんどん言ってほしいと思っているよ」という大人の気持ちを表すワークショップを中学生向けに行いました。
中学校の授業時間をいただいて、2回、開催しました。
始めの回は、みんな緊張していたようでしたが、2回目には活発に意見が出ました。
さらに、提案を分かりやすく伝える工夫と共有をしました。
ワールドカフェ、共有の方法、事前学習や成果のフォーマットなど
12人で13件も提案が出ました。みんなが思いを引き出しあった成果だと思いました。
ニュースレター第173号 中学生の想いを形に!
ご覧ください。
民主主義とマイクロアグレッション
2026-02-04 | ブログ
『こどもと民主主義をつくる 教育にできること』藤原さと 平凡社 2025年
を読みました。
 (https://www.heibonsha.co.jp/book/b669953.html)
(https://www.heibonsha.co.jp/book/b669953.html)
タイトルに惹かれて…
学校教育の段階での民主主義を体感するって大切なことだなぁと思っていました。
文部省(当時)が著作の教科書『あたしい憲法のはなし:民主主義』1947(昭和22年)が出版されました。
文部省も戦争の反省から、文部省の当時の役人ががんばって子ども達に伝えよう!として書いた、というのがとっても伝わってくるご本でした。
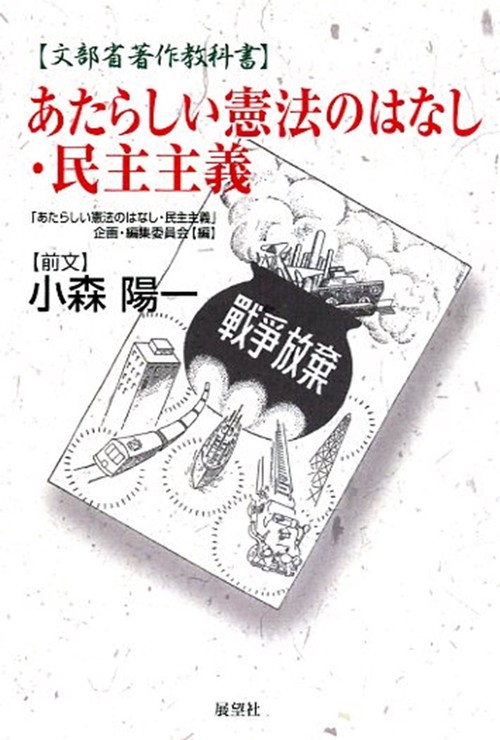
『あたしい憲法のはなし』は青空文庫にありました。https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
そして、
社会人大学院生の頃、スウェーデンの社会科の教科書『あなたの社会』を読みました。
そして、当時は、いくつかの教育に関係する本を読みました。
一番のオシは識字教育のパウロ・フレイレ(NGO活動をしていらした方から教えていただきました)
そして、当時は難解だなぁと思っていたジョン・デューイ
民主主義とマイクロアグレッション
そんなこんなで、民主主義と教育の関係(どうやって、子ども達に伝えるのか?)が気になっていました。
『こどもと民主主義をつくる』では、幼児期、小学校、ティーンエイジャー、成人の各段階での民主主義の教育(デンマークや国内での事例のも含めた)紹介がありました。
マイクロアグレッションが出てきたのは、ティーンエイジャーのところです。
P146~に社会的・構造的な抑圧をか開放する力のある教師を育てるという節があります。
ティーンエイジャーは社会の不平等や抑圧にも目が向く時期であるため、このタイミングで社会の構造に対して批判的に検討すrう力をつけるのが良いと書かれています。

気が付いた抑圧を知り、解放に向かうための3つのステップが書かれています。
STEP1:自分と向き合う(アイデンティティ、ポジショナリティ:マジョリティ・マイノリティ、バイアス、特権性)自分はどこにいるのか?を主観的、客観的に考えます。
STEP2:身近なコミュニケーションにおける抑圧を考える(言説、マイクロアグレッション)
STEP3:組織的・構造的な抑圧を解放する(意識を解放する、教室を解放する、カリキュラムを解放する、認知能力バイアスを解放する、コミュニケーションを解放する
これを改めて眺めると、自分を批判的に見ることから始まり、周囲を批判的に見る、そして、社会システムというおおきな塊を批判的にみるという順で検討していくことのようです。そして、批判の呪縛を解放していく…
これは、個人の意識の解放でもあるようです。
この中に、マイクロアグレッション!
抑圧は、権力者だけのものではなく、身近にあるということで、STEP2に位置付けられているようです。
マイクロアグレッションの内容は、3つの段階に簡単にまとめられています。
(マイクロアサルト:攻撃、マイクロインサルト:侮辱、マイクロインバリテーション:無化)
最後に対処の方法がありました。
意識しすぎると会話ができなくなってしまうのでは?ということで
学校は
「マジョリティとマイノリティが出逢い、共に学ぶ空間でもあるため、違いを超えて安心して話し合える関係を築くには、『慣れ』と『対話』が必要である(p173)」
「まずは、自分の言動を振り返りつつ『やらかしてしまったかも?』と思ったら本人に確認して謝るように心がけることからスタートするのが良いだろう(p173)」
とありました。
お互いに、「私、やらかした?」「うん」or「ううん」という会話や対話ができるのは、大人になって社会に出てからでは、なかなかできないことですよね。
学生のうちだからできることでもありそうです。かといって、もちろん、何を言ってもいいという訳ではありませんが。
民主主義とマイクロアグレッションがこんなに密接にというよりも、マイクロアグレッションに気づくことが民主主義をつくるために必要なことだったのですね!
マイクロアグレッションもそうですが、このご本には、パウロ・フレイレやジョン・デューイ、そして、何度もご紹介している『ダイアローグ』のデビット・ボウム、そして文部省の『民主主義』まで、オススメの本が重なっていることも、とてもうれしいことでした。
こどもと一緒につくっていけるといいな、私にできることは何か?と楽しく考えさせてくれた1冊でした。
出会いに感謝です!
ANNUAL REPORT2026 完成いたしました
2026-01-27 | ニュースレター
2025年のANNUAL REPORT 出来上がりました。
昨年も、みなさまのお蔭でいろいろなき機会をいただきました。
・子ども達とのワークショップ
・高校生がやりたい!と始めた高校生の高校生による「高校生子ども食堂」
・戸外での「クロスロード」
・自治体の来年度の方針を考えるワークショップ
などなど、マンネリにならず、新しいことに挑戦しながらワークショップや研修などを行ってきました。
みなさまに感謝しております。
今後とも、よろしくおねがいします。
株式会社ソーシャル・アクティ
代表取締役 林 加代子


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370