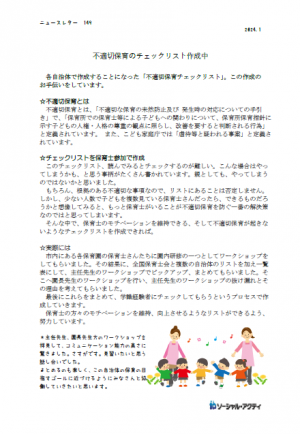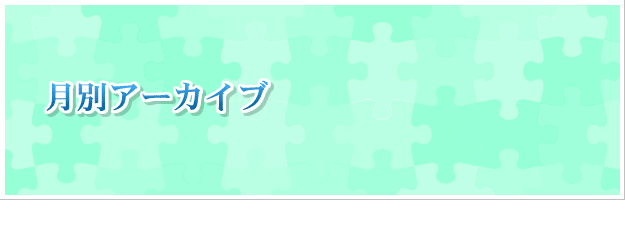
『檻の中のライオン』講演会に行きました
2024-02-26 | ブログ
1月21日に名古屋弁護士会主催の講演会に行ってきました。
『檻の中のライオン』を書かれた楾大樹弁護士の講演会。
ちらっと読んでいたこのご本の著者の話が聞ける!ととても楽しみに
(サインしてもらう!と思い、本も持って!)行きました。
会場は暖かかったものの1月。なのに、ご本人は半袖のTシャツ1枚。
寒くないのか?後から1枚着るのか?と要らぬ心配をしてしまいました。
ずっとTシャツ姿でしたが、公園が始まると、なるほど~寒くない理由がと分かるのでした。
(とっても軽快だけれど、スピーディ。しゃべりまくりな感じでしたので熱くなり、Tシャツ姿でなければ、持たないのだと納得)
受付でいただけるのは、なんと憲法99条全てが書かれたクリアファイル!
ご本の中に出てくるライオンのイラストも入って、ちょっと見る気になれるものでした。
(文字だけが並んでいると、見る気力が…。イマドキはデザインが大切と思いました)
ご講演では、何度もこのクリアファイルを開いて、条文を確認する場面がありました。
なので、便利便利。
そしてなんと!参加者の中に小学校5年生の子どもが~
きっと一緒にいらしたお母さまの影響なのでは?と思うのですが、
講演中は積極的に発言していて、頼もしい!未来はまだ明るい!と思わせてくれました。
講師の楾さんもついつい、その子に振ったりして(笑 気持ちは分かります)。
 (楾さんのfacebookより)
(楾さんのfacebookより)
檻の中のライオン?
このご本、ライオンの話でも、動物園の話でもなく…
クリアファイルに書かれている「憲法」の話です。
ライオンは権力者。檻は権力者の力を封じ込める憲法だったのです。
学生の時に、授業で先生が言ってたなぁと思い出しました(笑)
改めて確認!
憲法第99条にありました。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
憲法は、一人ひとりの力は弱い国民に向けたものではなく、権力を持った、法の執行、法を作る人たちに向けられたものでした。
権力は濫用されがちなので、檻を造って権力を入れておこう!というものなのですね!
何を守るのか?
それは、国民主権、基本的人権、平和主義
この3つの原則を守るのが憲法でした。
これらを守るよとライオンに言っているのでした。
先日から私の課題となっている「マイクロアグレッション」(FAJの定例会でやってみました)は、掘り下げて考えると、基本的人権を侵すものでした。
(人権侵害するのは、このときは国民の間ですが。守るように仕組みを整えるのがライオン)
今のテーマにはまっていることに、ちょっとうれしく、やっぱりねと思える時間でした。
いろいろなことが、憲法レベルで守ろう!と宣言されているというのは、心強いことでした。
最後の最後、どんな法律が該当するのか?分からない、判断ができないときは、憲法のどの条文に記載されているのか?はとても大切だよね、と思いました。
そして、それは「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(第12条)」とありました。
そうかぁ。誰かにお任せではいけないのね。
まずは、憲法を知ることからから!始まるのですね。
そのためにも、このクリアファイル、使い易いです。
手軽に一覧できます。
あれ、それはどこにあるの?とササっと探すことができました。
(それを想定していらっしゃるのだろうと思います)
せっかくいただいたクリアファイル。
いろいろとふりかえってみるときに、隣においておくと、よりふりかえりが深まりそうです。
半袖Tシャツを着て考えてみようかなと思う、熱い講演会でした。
ファシリテータ―としては?
基本的人権の自覚はファシリテーターとしても大切。
マイクロアグレッションでも、話している最中に、今の発言は差別意識が根底にないだろうか?を考えて、介入しなければなりません。
とても、瞬発力が求められます。
瞬間に「これは、差別。この人はどこまで自覚して発言したのだろうか?非難にならないような指摘の仕方は?」など、考えなくてはなりません。
普段から、マイクロアグレッションなのか?この場合はどうなるのか?を気にして話し合いの場にいるようにしなくてはなりません。
まずは、「?」と思う発言を検討して(発言しなくても良いから)にも参加してもらって…
できれば、皆さんにも参加してもらって
個別の事例をか差寝ていくのがbetterではないかとおもっております。
ニュースレター第149号「不適切保育のチェックリストを作成しています」
2024-02-05 | ニュースレター
全国の自治体で作成することになった「不適切保育チェックリスト」
いろいろな自治体が作成しています。
このチェックリストを現場(保育士、主任、園長)参加で作成しています。
作成の段階から関わっていけば、よりリストへのコミットが高まるのでは?とも考えています。
保育士さん達が前向きになり、「よし、こんな風に子どもと楽しもう!」と思ってくれるようなリストができることを目標にしています。
ニュースレター第149号「不適切保育のチェックリストを作成しています」
以下、ご覧くださいませ。
「言語化する」は、大切なことでした
2024-02-05 | ブログ
先日、Youtubeを見ていたら、精神科医の樺沢紫苑という方の動画ができてきました。
タイトルは「言語化の魔力」https://www.youtube.com/watch?v=hMLnssh08Nk&t=1880s
『他者の靴を履く』で、言語化の必要性を感じていたので、見てみました。
『他者の靴を履く』では、刑務所にいる人たちには言語化することが苦手な人が多い、とのことでした。
自分の気持ちや考えをうまく言葉にできないで、もやもやしている状態が続いていると、そのもやもやが暴力的に発現してしまうのだと。
言語化するということは、人間の生活にとって、とても重要なことなのだと思いました。

そこで、精神科医のいう「言語化の魔力」とは、どんな力なのか?
とても興味を持って拝見しました。
言語化で悩みを解消する!?
樺沢先生によると…
悩みがあるという人が3/4
悩みがないという人が1/4
悩みがなかなか解消しない人3/4
悩みが比較的解決している人1/4
というアンケート結果があるそうです。
悩みがない人は、比較的解消してしまうから「ない」のでは?という仮説が立ちます。
「悩み」は、ツライ、苦しい、逃げ出したいもの。
そして、対処法が分からない、停止・停滞感がある←これが辛い…
「悩み」を解決することは、原因を取り除くこと!と思うと、なかなか取り除けないことが多い。
他人が原因だったりすると、もうムリ!って思いますよね。
←だから、悩むのですよね。(ぐるぐると回っている感じで、出口が見つからないイメージですよね)
ところが!「悩み」の原因を取り除かなくても、悩みは解決できる!とのこと。
解決ではないかもしれないが、少しずつ解消していけば、いつの間にか気にならなくなっている!と。
その時に活躍するのが「言語化の力」で、無意識の思考(ストレス)を言語化して意識するとスッキリする効果がある。
悩みの原因は自分ではどうにもならないことがあるので、自分でコントロールできることに意識をずらすということも悩み解消の1つ
「それは、それとして」「今できることは?」など、自分でコントロール可能な、ポジティブな言葉にするのがコツ
自分でコントロールできることは、自己効用感がアップし、
なんとかなるさと思えると、楽観性が上がり、緊張感が下がり、仕事力がアップするというスパイラルも期待できるそうです。
きっと自分の中で、「それはそれとして」という時に、それって何?を言語化し、認識すること
その後で、「今できること」を言語化して行動に移す。
言語化することで、悩み解消のステップが見えてくるのかもしれません。
先が見えると、安心できますよね。

コミュニケーションの効用
さらに、「コミュニケーションは癒し」になるそうで、会話交流の際にオキシトシン(不安や心配を緩和しストレスを減らすと言われているホルモン)が分泌されるそうです。
会話には、言語化は必須。
その方法は、声でも手話でも。言語化することには変わりないですよね。
言語化の魔力、まだまだありそうです。
どうやって言語化するの?ということを聞かれたことがあります。
どう説明するんだろう?
次の課題にしようと思います。
ファシリテータ―は、コミュニケーションの場にいます。
いるというよりも、円滑に話し合いが進み、実のあるものになるかをデザインします。
そのとき、参加者が言語化するお手伝いをすることもあります。
言語化することをさらっと何気なく説明できると、話し合いの場がより円滑になる!と思いました。
まだまだ、学ぶことが多い!と思った動画でした。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370