
民主主義とマイクロアグレッション
2026-02-04 | ブログ
『こどもと民主主義をつくる 教育にできること』藤原さと 平凡社 2025年
を読みました。
 (https://www.heibonsha.co.jp/book/b669953.html)
(https://www.heibonsha.co.jp/book/b669953.html)
タイトルに惹かれて…
学校教育の段階での民主主義を体感するって大切なことだなぁと思っていました。
文部省(当時)が著作の教科書『あたしい憲法のはなし:民主主義』1947(昭和22年)が出版されました。
文部省も戦争の反省から、文部省の当時の役人ががんばって子ども達に伝えよう!として書いた、というのがとっても伝わってくるご本でした。
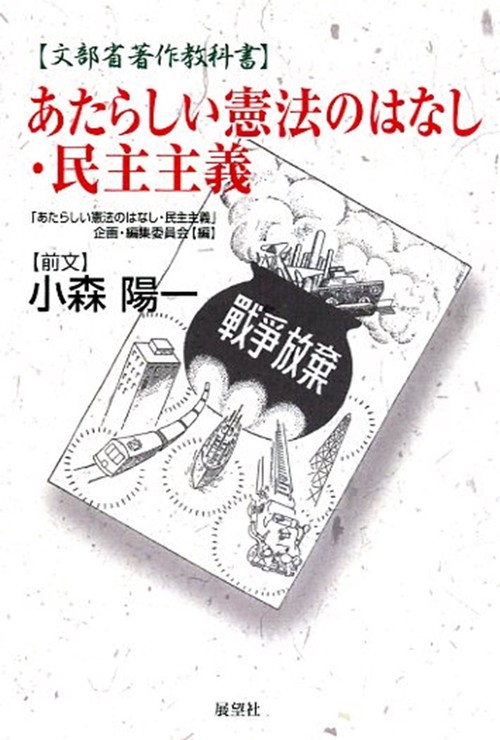
『あたしい憲法のはなし』は青空文庫にありました。https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
そして、
社会人大学院生の頃、スウェーデンの社会科の教科書『あなたの社会』を読みました。
そして、当時は、いくつかの教育に関係する本を読みました。
一番のオシは識字教育のパウロ・フレイレ(NGO活動をしていらした方から教えていただきました)
そして、当時は難解だなぁと思っていたジョン・デューイ
民主主義とマイクロアグレッション
そんなこんなで、民主主義と教育の関係(どうやって、子ども達に伝えるのか?)が気になっていました。
『こどもと民主主義をつくる』では、幼児期、小学校、ティーンエイジャー、成人の各段階での民主主義の教育(デンマークや国内での事例のも含めた)紹介がありました。
マイクロアグレッションが出てきたのは、ティーンエイジャーのところです。
P146~に社会的・構造的な抑圧をか開放する力のある教師を育てるという節があります。
ティーンエイジャーは社会の不平等や抑圧にも目が向く時期であるため、このタイミングで社会の構造に対して批判的に検討すrう力をつけるのが良いと書かれています。

気が付いた抑圧を知り、解放に向かうための3つのステップが書かれています。
STEP1:自分と向き合う(アイデンティティ、ポジショナリティ:マジョリティ・マイノリティ、バイアス、特権性)自分はどこにいるのか?を主観的、客観的に考えます。
STEP2:身近なコミュニケーションにおける抑圧を考える(言説、マイクロアグレッション)
STEP3:組織的・構造的な抑圧を解放する(意識を解放する、教室を解放する、カリキュラムを解放する、認知能力バイアスを解放する、コミュニケーションを解放する
これを改めて眺めると、自分を批判的に見ることから始まり、周囲を批判的に見る、そして、社会システムというおおきな塊を批判的にみるという順で検討していくことのようです。そして、批判の呪縛を解放していく…
これは、個人の意識の解放でもあるようです。
この中に、マイクロアグレッション!
抑圧は、権力者だけのものではなく、身近にあるということで、STEP2に位置付けられているようです。
マイクロアグレッションの内容は、3つの段階に簡単にまとめられています。
(マイクロアサルト:攻撃、マイクロインサルト:侮辱、マイクロインバリテーション:無化)
最後に対処の方法がありました。
意識しすぎると会話ができなくなってしまうのでは?ということで
学校は
「マジョリティとマイノリティが出逢い、共に学ぶ空間でもあるため、違いを超えて安心して話し合える関係を築くには、『慣れ』と『対話』が必要である(p173)」
「まずは、自分の言動を振り返りつつ『やらかしてしまったかも?』と思ったら本人に確認して謝るように心がけることからスタートするのが良いだろう(p173)」
とありました。
お互いに、「私、やらかした?」「うん」or「ううん」という会話や対話ができるのは、大人になって社会に出てからでは、なかなかできないことですよね。
学生のうちだからできることでもありそうです。かといって、もちろん、何を言ってもいいという訳ではありませんが。
民主主義とマイクロアグレッションがこんなに密接にというよりも、マイクロアグレッションに気づくことが民主主義をつくるために必要なことだったのですね!
マイクロアグレッションもそうですが、このご本には、パウロ・フレイレやジョン・デューイ、そして、何度もご紹介している『ダイアローグ』のデビット・ボウム、そして文部省の『民主主義』まで、オススメの本が重なっていることも、とてもうれしいことでした。
こどもと一緒につくっていけるといいな、私にできることは何か?と楽しく考えさせてくれた1冊でした。
出会いに感謝です!
マイクロアグレッションを受け続けると?
2026-01-25 | ブログ
マイクロアグレッションのワーク開発中
2024年2月にFAJ(日本ファシリテーション協会)の定例会で「マイクロアグレッション」を取り扱って以来、
2025年3月、今年2026年3月でも挑戦しようと企画中です。
マイクロアグレッションはひとことで言うと、針でちくっと刺されたくらいの差別的な言動(与えたほうは無意識で、与えられたほうはあまりにも自然に通り過ぎるので、自分が過敏なんだなと納得してしまうことが多い)というようなものだと、とりあえず想定しておいてくだされば。
そのマイクロアグレッションを取り上げた定例会のレポートは、以下をご覧ください。
2024年は、人権、人権デューデリジェンスとマイクロアグレッションを中心に
https://www.faj.or.jp/base/chubu/news/20240217-microaggression/index.html
2025年3月は、アンコンシャスバイアス(いろいろな差別意識)をマッピングを中心に
https://www.faj.or.jp/base/chubu/report/20250315-233-1/index.html
どこをフォーカスして、どう伝えたら伝わるのだろう?と試行錯誤を続けています。
盛り込みすぎだったかなかな?とか、なんとなく自分事としてまだ伝わっていないのでは?とスッキリできていません。
ということで、今回の定例会ではマイクロアグレッションの影響を考えてみようか?と考えています。
マイクロアグレッションの影響
https://www.youtube.com/watch?v=mktQelp3UcI
「脳科学者と学ぶ 知らないと損 完全版 人を一番早く潰す方法 10分徹底解説」
↑のYouTubeがたまたま上ってきまして…(アルゴリズムに感謝)
何気なく流していたところ、「マイクロアグレッション」という言葉が出てきました。
そこからは、もう、手を止めて凝視(笑)
この中で、マイクロアグレッションを浴び続ける(1日に10回くらいチクチク)と心が壊れていくという恐ろしい影響を知ることになりました。
簡単にピックアップすると…
(上司に細かいところをいちいちチェックされる、それも具体的な指摘ではない場面をイメージしてくださると分かりやすいかも)
1.自分で考えて決める脳の分野が破壊される(2週間で細胞が半減!)
2.恐怖記憶の形成(なんと、PTSDと同じメカニズム!)
3.学習性無力感(どうせ、無駄と思ってしまう)
4.自己価値の消失(自分の価値=0 と思い、生きる意味を失う)
5.支配構造の完成(あなたがいないとダメと思う)
こんな恐ろしい影響があったのです!
支配されてしまうのですね…(まるで奴隷?それを利用した事件ってたくさんあるような気がします)
このプロセスを、どの段階で止めるかが大切なのですね。
壊れてしまってからでは、立ち直るのは難しそう(立ち直るとしても時間かかるだろうなぁ)
もちろん、対策も言われていましたので、ご紹介しますね。
1.記録をとる(指摘された内容、日時をすべて記録する)←俯瞰して冷静になると「なぜ、こんなことを言われないといけないんだ?」と思うのでは?
2.物理的に逃げる(相手は変わらない)←逃げ恥ですね(笑)
3.専門家に相談する(カウンセラーや弁護士など)←相談するのに勇気が要りそう。背中を押してくれる人がいてくれるといいなぁ
☆境界線を引く勇気(=強さ)を持とう!←どこで、気づいて勇気を出すか?が課題な気がします。
ちょっと救われました。
もちろん、本も読んで裏付け中です(ファクトチェック?)
『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』デラルド・ウィン・スー著 マイクロアグレッション研究会訳 明石書房、2021年
 (アマゾン x.gd/OcWdA より)
(アマゾン x.gd/OcWdA より)
『無意識のバイアス 人はなぜ人種差別をするのか』ジェニファー・エバーハート著 山岡希美訳 解説 高文明 明石書店 2020年
 (アマゾン https://x.gd/U7SHC より)
(アマゾン https://x.gd/U7SHC より)
ここからは、ファシリテータ―のウデの見せどころ!
この3年の取組で、
マイクロアグレッションは、アンコンシャスバイアス(無意識の差別)が表出したものだと考えています。
そして、それは、その人の人権を侵害すること
という認識までたどり着きました。
その影響も大きいことが分りました。←いまここ
今度は、どう伝えたらいいのか?がテーマです。
子どもの人権については、クイズと対話で子ども達には届いているみたいです。
大人には、どんなツールを組み合わせると、納得!してもらえるか?
もっと試行錯誤を続けたいなと思います。
きっと、うまく伝わった!というプログラムができたら、抽象的な概念を伝えることに展開していけるのでは?と
自分に期待します(そうなってくれるハズ!)
分かりにくいことをカンタンに楽しく伝える方法を考えるのもファシリテーターの役割ですもんね。
3月の定例会が終わったら、また、ご報告します。
前回の「第三者の役割り…」学問的な整理がありました
2025-12-20 | ブログ
立命館大学アカデミックセンターというオンラインでも受講できる(しかも、無料の講座もたくさん!)時間も資金もうれしい講座があります。
ここで、今、3回シリーズの講座を受講しています。
それは…
【立命館大学超領域リベラルアーツ特別講義】
【教育ってなんだろう?】
不登校増加の背景と課題 -「生物・心理・社会モデル」で複合的な要因を読み解く
伊田勝憲先生
https://www.ritsumei.ac.jp/open-univ/course/detail/?id=413
この第2回目が12月19日にありました。
タイトルは「不登校とその前後のプロセス」
この中で、「ああ、第3者や祖父母の役割りってこれなんだな」と思いました。
なんて、タイムリー!!
という訳で、前回のブログの続編としたく。
伊田先生の1,2回のご講義では、BPSモデルに基づく不登校のお話をしてくださっています。
第2回では、ご自分のご経験も紹介してくださりながら…
さらに、少し(笑)を入れて。
なので、とても興味深く90分があっという間に終わってしまいます。
 (不登校のイラストを探すと、だいたいこんなイメージで、暗いです。)
(不登校のイラストを探すと、だいたいこんなイメージで、暗いです。)
さて、本題。
BPSモデル?
講義のタイトルにある、「生物・心理・社会モデル」が「Bio Psycho Social Model」で略してBPSモデルというそうです。
このモデルは医療の分野の考え方とのことで、(全く門外漢なので、そんな考え方があったのか!と目から鱗でした)精神的疾患を分析、回復に向けての分析モデルのようです。
Wikipediaの引用ですが、「生物心理社会モデルの基本的な前提は、健康と病気は生物学的、心理学的、そして社会的要因の相互作用の結果であるというものです。この概念は健康心理学において特に重要です。これを1977年に理論化したのがジョージ・L・エンゲル https://en.wikipedia.org/wiki/George_L._Engel」とのことです。
B(Bio ):生物:遺伝、生理機能、病原体、解剖学、脳の機能など、身体的・医学的な要因。
P(Psycho):心理:感情、思考(認知)、ストレス、対処行動、性格、信念など、個人の内面的な要因。
S( Social):社会:家族関係、職場環境、経済状況、文化、人間関係、社会福祉など、個人の外部環境や社会的な要因。
(:以降の項目はAIが教えてくれました)
講義では、先生の実体験をBPSモデルで解析してくださいました。
例示があったので、とっても分かりやすいです。
この事例の中では、身体的(B)の要素があり、これに社会(家族が一番小さな社会として)が影響していた。
(登校することが良いというのではないのですが)
伊田先生が不登校から登校へ変わったのは、新しい社会との接点があったことのようです。
祖父母の役割りっぽいこと
中学生の時、不登校でひきこもりのようになっていたときに、(地域の異なる)小学校の頃の趣味仲間から電話があり、出かけてみた。
この電話をきっかけに、違う世界に触れて(というか、好きだったことを思い出して)、登校するようになったとのことでした。
ここで、家族という小さな社会(学校もある意味、小さな社会?)に、新しい異なる社会(上の場合は、趣味仲間がいる社会)が異なる視点を見せてくれたのでは?
と思いました。サードプレイスとというのかもしれません。
家族だけでは、、できないこと。(普段、生活していても閉そく感があるときもありますよね)
ここに、他人が違う社会を見せてくれる、いつもと違うフレッシュな空気を吸わせてくれると、ハタ!と気づくことがある。
それがきっかけになって、適応していく…
もう一つの社会、新しい空気が、第三者であったり、祖父母であったりするのだなぁと思いました。
視点を変える、他のことにも目を向ける、ということが大切なことなのだと。
たぶん???が多いと思います。
伊田先生の論文をご紹介します。
http://file:///C:/Users/NEC-PCuser/Downloads/e_71_6_ida%20(1).pdf
大きくくくっちゃうと
地域ぐるみで子どもを育てる、子育ての社会化と言われて久しいですが…
おじいちゃん、おばあちゃん、ご近所で顔見知りのおじさんおばさん(昔は知った顔の人たちに囲まれていましたよね)などの第三者が、声をかけてくれる…安心できる…
それが、今言われているサードプレイスの一つの機能かもしれません。前回で言いたかった祖父母の役割りでもあるのかも。
親子だと、関係が緊密ですもんね。息抜きの場が必要なのかも。
余談…
講義の中で、いじめのダメージについてお話がありました。
大きく1回(10として)
小さく1回(1として)
小さな1回が時間差でくる(5回くらい?)
とすると…
時間差でくる>大きく1回<小さく1回
小さくでも時間差でくると1×5 ではなく、5×5のダメージがある。乗数でダメージがある。
これは、とても納得しました。
小さなジャブが何回もあると、ツライですよね。
アニメ「あしたのジョー」で、ジョーがぎりぎりまで耐えている姿が浮かびました。
上の例示とは異なりますが、あしたのジョー症候群というのもあるそうです💦
子育て中の祖父母の役割りは貴重かも
2025-12-19 | ブログ
子育て支援の一般社団法人の監事をしています。
その中で小学校1年生かから3年生までの放課後の預かりのお手伝いもしています。
https://kodomo-kurasu.net/ (←こちらです)
私の担当は、月に1度の「子ども哲学」と月に2回の「ソロバン体験」
もちろん、ピンチヒッターもします(笑)
1時間くらいなのですが、いろいろと感じる事があります。
個人的な感想だと思って、ご高覧いただけるとうれしいです。
その子に合わせたプログラムを
おしゃべりや工作が好きな子が「子ども哲学」
どうやら数字に興味のある子が「ソロバン体験」に来てくれています。
今、丁度、1人ずつなので、ゆったりとその子の様子をみながら1時間を過ごします。
たまに、他の子もいると一緒になってやっています。
ゆったりとやらせてくださる代表のお陰もあって、子どもも私も楽しい時間です。
その中で感じたことは、
1:1で自分の興味のあることを伸ばしてくれることが、子どもにとって、楽しいんだなぁということでした。

おしゃべりが好きな子には、哲学というよりも、おしゃべりの中でいろいろな話を引き出して、グラフィックしていく!
保護者がお迎えにきたときに、「こんなことお話したよ」の成果を子どもから渡すと、みんながハッピーな気持ちになれます。
先日は(キャリア教育っぽく)ご両親のお仕事はどんなことしているの?を具体的に掘り下げて聞き、グラフィックしました。
日常の会話で出てくる、ご両親の仕事内容。
それを一覧にしていくと、どんなお仕事なのか具体的に広がって行き、インターネットで検索するとさらに理解がふかまったようでした。

ソロバン体験では、そろばんの方は、今日は何枚やる?と目標を決め、それが終わったら数に関する楽しいことをしています。
ソロバンの桁に点があるので、どんどん左へ移動させて桁を大きくしていくと、いくつまで行ける?とか、桁の単位はいくつまであるの?とか…調べて、書いて行きました。
そして、一緒に声に出して読む(笑)
また、あるときは計算をしました。
10000-(任意の数字)3-4-7-6-‥‥という問題をA4の紙いっぱいに書いて、計算しました。
方法は10になるペアを丸で囲んでいき、いくつ10ができるか?を探していきました。(足して10にするのはソロバンの考え方ですもんね、と理由をつけて)
最後は、私がソロバンで計算して、答えを書く。
という、その子と私の合作(笑)
小学生は(年齢+1分)が集中力が続く目安だと書かれていました。
それが、自分の好きなことであれば、30分でも40分でも集中できました。
(この中に書かれていました)
もちろん、保護者さんも成果物を見て、喜んで、子どもさんを褒めてくださいました。
私も含めて、みんなHAPPYになれました。
第三者がいることが大事
これらのことから感じるのは、第三者が子どもと付き合うという事です。
つきあうというか、同じ時間をその子を中心にしてゆったりと過ごす時間が大切。
ということでした。
もちろん、保護者と過ごすことは大事なのは大前提ですが。
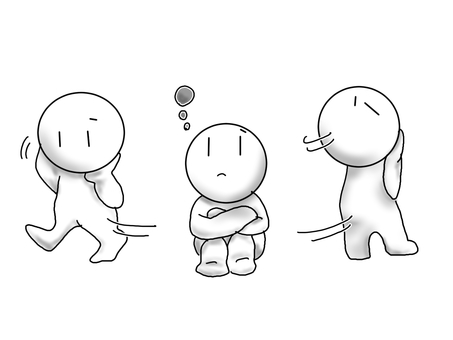
損得抜きで、否定せずにその子と向き合って、認めてくれる人も必要なのですね。
(イマドキの子は特に、否定されない、何を言っても間違いではない、ということがうれしいようです。)
子育てが終わった今、分かることは、親をしていると(特に子どもが小さいと)気持ちの余裕がなかったなぁということです。
第三者だからこそ、親ほど濃厚ではない関係で冷静に対応できる。
そういう存在がいると感じることもいい影響があるような気がします。
きっと、サードプレイスが必要と言われる意味は、こういうことなのかもしれません。
核家族が多い中、ちょっと薄い関係で、見守ってくれる存在は貴重なのだと思いました。
きっと、祖父母のような存在なのでしょう。
親とは違う、無条件でカワイイと見守ることができる役割(子どもと心の距離を取らないとできませんよね)
改めて、放課後預かりの中で、そんな存在を感じてもらえると、うれしいし、目指そうと思いました。
追記…
その子に合わせたプログラムをアドリブで考えるのですが、
子どもがいつもヒントをくれます。
お話の中で、パパのお仕事の話が出たら、そこを広げたり、深めたりしていく
ソロバンをしているときに、桁を聞いてくる。だったら、ついでに調べちゃおう!
など、子どもが始めたことを進化させるのです。
これは、アドリブ?
面白がる気持ち?
きっと、インプロですね!
ファシリテーションの要素にも取り入れたい、インプロ。
もっとブラッシュアップしていけば、もっと子ども達と楽しい時間が過ごせるのでは?と思うのでした。
アートとまちづくり(香川県直島)
2025-11-30 | ブログ
前回の「アートとデザイン」の話から、今回は「アートとまちづくり」へ。
(AIのお話にしよう!と思っていたのに、アートの印象が強すぎて…)
アートの島で有名な香川県直島、その前のもろもろの方が気になっていましたが、友人が直島へ移住したので、思い切って行ってきました。
アートの島になる前のもろもろ…
もろもろ・・・
それは、30年以上前からあこがれてい憧れていた弁護士故 中坊公平さん(https://x.gd/uJyUZ)が絡んでいたので、有名な豊島事件がマスコミに取り上げられた当時ウォッチしていたのでした。
今回訪れた直島の隣にある豊島(てしま)で産廃の投棄(住民には、無害な廃棄物と伝えられていたのが、徐々に有害な廃棄物が投棄され、健康被害が出るようになった)があり、住民の反対運動を弁護士として支えたのが、中坊公平さんでした。
豊島事件の詳細はこちらからhttps://www.teshima-school.jp/struggle/history/
バブルの清算をする住専(住宅金融債権管理機構)の代表となった頃、それ以前の森永ヒ素ミルク事件や豊田商事の破産管財人を務めたことなどを知りました。(この頃、全国市民オンブズマンが活動を始めたこともあり、やっぱり、弁護士は正義を実現するために頑張ってくれる人!なんて希望も込めて思っていました。)
産廃を受け入れることにした直島には、お金がつぎ込まれることになり、ベネッセも投資して(https://benesse-artsite.jp/about/soichiro-fukutake.html)アートの島で有名になったのでした。
アートの魅力
アート(特に近代)は、よく分からないなぁと思っていたのですが、行ってみると(ロケーションを活かしたアートでもあったので)、前回のキーワード「感性」が刺激された気がします。
特に、移住した友人がアート対話をしてくれて、とても深い鑑賞となり、見方や感じ方が少し変わったような。
(直後に参加したFAJの定例会では「島流し研修を名古屋で体感する」で、一人で30分内省して、対話するというプログラムでしたが、一人の時間で過ごしたお部屋の詳細なディティールに気が付いて、とても楽しい時間となりました。そこで、「あ、感じ方が変わった気がする…」と自分の変化に気づいたのでした。)
それは、
島民なので無料という施設がいくつかあって、一人で行ったり、島を訪れた友人・知人を案内したり(先日は、アートのワークショップにも参加したそうです)と何度も作品を鑑賞していて、問いかけでで、いろいろと引き出してくれたり、深掘りしてくれたりしてくれたお陰だと思っています。
アート対話、アートとファシリテーションという分野がありますが、こういうことなんだなぁと体感しました。
まちづくりの視点から
前置きが長くなり過ぎました💦
訪れたのは、瀬戸内国際芸術祭(https://setouchi-artfest.jp/)が終わった直後でした。超繁忙期が終わったところへお邪魔しました。
政情もあり、特定の国からの観光客は少なかったのですが、
欧米の人が多くアートを楽しみに、滞在型で来ているんだろうなぁと見える人達がたくさんいました。
(日本人観光客よりもダントツに多く、富裕層が多いように見えました。)
円安も手伝っているのかもしれませんが、優雅にアートを見て回っているというのが伝わってきました。
(マンダリンホテルも建設中!)
レンタサイクル(しかも電動アシスト!)が充実して、島ライフを楽しめるように整備されていました。
観光は、1次、2次、3次産業が潤うと言われています。
さらに、若い人(国籍問わず)がアートの力、集客力に惹かれて、移住してきていました。
(直島の20~60歳の人口動態 直島町HPよりグラフ化)
分かりづらいグラフなのですが、直島にベネッセが直島に投資を始めたのが、1989年(平成元年)にキャンプ場がオープン。
その後、ベネッセハウスがオープンし、
上のデータの始まる1998年(平成10年)には、家プロジェクトが始まったのでした。https://benesse-artsite.jp/about/history.html
グラフを見ると、2006年(平成18年)までに50~54歳台が減り、2012年(平成24年)までに55~59歳台が減っています。
ところが、島から減っていくことが多い20代、30代(特に25~30歳、45~49歳)が増減するものの、横ばいとなっています。
少し、見づらいので、社会動態に注目してみると…
(直島町HPよりグラフ化)
上のグラフのように、社会的な要因での人口動態をみると、令和3年には社会増が社会減の人数を上回る傾向となっています。
観光客に向けた仕事があるので、若者が移住してくるのでは?という仮説が成り立ちそうです。
アート→観光客増→仕事増→移住者増ということでしょうか?
余談ですが…アートのエピソード、もう一つ
直島にある漆芸ギャラリーにお邪魔しました。
直島のステキな漆器を扱っています。
ここで、丁寧なご説明をいただいたのですが、なんと!世界的に有名なIT会社のデザイナーさんが複数訪れていらっしゃるとか。
そこで、説明すると感動して帰られるのですが、後日、そこの製品をみると…
「もしかしたら、この部分は、あの時の?」と思うことがあるそうです。
日本の伝統文化もアート(デザイン?)として捉えると、デザイナーさんの感性を刺激するのですね!
ファシリテータ―としては、感性は充分に刺激されました。
が!
アート対話という場面でのファシリテーションも、とても興味深いことが分りました。
どのようにファシリテータ―が問いかけるか?で全く異なるアウトプットになるのだなぁと思いました。
ファシリテーションの世界は、広くて深い。
気持ちのあう、感性を刺激するアートなファシリテータ―に会えるというのは、幸せなことだと思いました。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370





