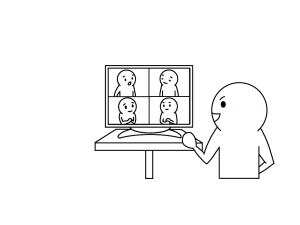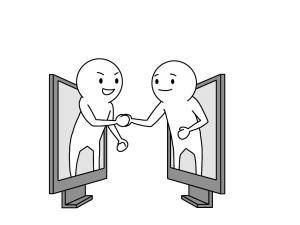オンラインでのグループワークの回想
2021-04-21 | ブログ
4月は新学期が始まりますね。昨年の今頃は、学校一斉休校でした。大学の授業もオンライン(オンデマンドも含みます)に切り替わる準備を各大学が始めていた頃でした。
その時に感じたことを備忘録としても書いておこうと思います。
 (教科書はこれです)
(教科書はこれです)
授業でもグループワークをしたい!
どんな授業にしたのかというと…
基本は、グループワークしたい!です。(授業も「人間関係とコミュニケーション」なので)
①動画を作成し、YouTubeに流しておく
②授業時間にデバイスの前に集まってもらってオンラインでの授業
簡単なレクチャーとグループワーク
③ふりかえりシートは、後で提出
という流れで行っていました。
②のグループワークでは、
大学がGoogle meetを使っていましたので、4~5人程度のグループ表を作成してグループ分の部屋を設定しておきました。
複数回、グループワークを行うときは時間を提示して一旦、はじめの部屋に戻ってきてもらいます。
そして、レクチャーの後、再度グループワーク
その後、グループワークが終わったら自由に解散
としていました。

授業をして分かったのは…
15回の授業の中で、途中で2回だけリアルな対面授業ができました。
(その後、すぐにオンラインに戻ったのですが)
これがとっても影響が大きかったのです。
2度、リアルに対面の授業を行ったことで、グループワークの進め方についての要領を理解してくれたようでした。
次にオンラインの授業に戻っても、今度はサクサクと学生同士で進めてくれました。
きっと、初めてに近いグループワークだったので、手探りというか「これでいいのかな?」と不安を抱えて行っていたのだと思います。
リアルであれば、教室内を回って分からないところは直接指導できるのですが、オンラインだとなかなかそうはいかなかったこともあります。周りのやり方をみてやってみるということもできず…
ちょっと可哀そうでした。
ところがリアルでは、周りには同じグループワークをしている学生がたくさんいて、話し声も聞こえるので雰囲気も明るく、分からないことはさっと手を挙げて聞けるという、とても開放的な場にいることができたのです。
「これでいいんだね」「こうすればいいんだね」を確認することもできたので、今度は自信をもって進めることができたようです。
(グループに入って、聞いていても随分と活発なワークになっていました)
授業は2年生が対象でしたので、1年生のときに顔を合わせていたことも大きかったようです。
これからの時代に身に着けようと思うことは
一度でも、リアルでグループワークを経験していることの大切さを知りました。
そこに甘えずに、オンラインのみでも、グループワークを進めることができるようにレクチャーする力をつけたい!と思います。
オンラインの便利さも分かってきたので、授業に、そして、まちづくりの話し合いに、両方のいいところを活用できるようにしていきたい!とも思っています。
急激に、本格的に訪れたオンラインの時代。
使いこなせるように試行錯誤が続きます。
『何とかならない時代の幸福論』
2021-04-13 | ブログ
『子どもたちの階級闘争』を読んで以来、興味をもって拝読しているブレイディみかこさんの対談本を書店で見つけ、どんなことが書かれているのか?楽しみに購入してきました。
 (https://www.amazon.co.jp/子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から-ブレイディ-みかこ/dp/4622086034/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=子どもたちの階級闘争&qid=1618278558&sr=8-1)
(https://www.amazon.co.jp/子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から-ブレイディ-みかこ/dp/4622086034/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=子どもたちの階級闘争&qid=1618278558&sr=8-1)
ブレイディさんは、若い頃に単身で渡英し、現地の方と結婚。
『子どもたちの階級闘争』では、教会が運営している保育園に保育士として勤めていた頃の様子が書かれていました。
政権の考え方によって、こんなに保育(しいては国の教育方針に違いが生まれるのか!と思った記憶があります)
ご本では、最下層の子どもたちが通う保育園と表現されていました。
『何とかならない時代の幸福論』では、鴻上尚史さんとの対談が収められています。
第1部では、NHKの番組で対談した内容、第2部ではこの本のために対談した内容が書かれています。
 (https://www.amazon.co.jp/何とかならない時代の幸福論-鴻上-尚史/dp/4022517417/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=子どもたちの階級闘争&qid=1618278558&sr=8-5)
(https://www.amazon.co.jp/何とかならない時代の幸福論-鴻上-尚史/dp/4022517417/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=子どもたちの階級闘争&qid=1618278558&sr=8-5)
共感する箇所はたくさんありましたが、中でも印象に残ったことを一つご紹介します。
シンパシーとエンパシー
シンパシー(sympathy)とエンパシー(empathy)は違うのだということでした。
p56
シンパシーは「もっと感情的に同情したり、同じような意見を持つ人に共鳴したりすることで、SNSなら『いいね』ボタンを押すようなこと」
エンパシーは「対象に制限はなく、自分と同じ意見を持っていない人でも同情できない人でも対象になりえるもの。この人の立場だったら自分はどう感じるだろうと想像してみる能力-アビリティ」
とありました。
アビリティ(ability)…
能力と言われると、よく目にするスキル(skill)との違いが気になりました。
調べてみると…
スキル:ある事柄をなすのに必要とされる特殊な技能・技術、特殊能力(「卓越」「熟練」などの特別なニュアンスが含まれている)
アビリティー:身体・精神的な実際の能力を表す一般的な語、能力(最も一般的な「能力」をあらわす
(http://mijitan.com/skill-abilityより)
ということでした。
ご本p56に戻ると「アビリティだったら伸ばせるし、伸びる」「エンパシーという能力を磨いていくことが多様性には大事」という言葉があります。エンパシー=アビリティということで、「人の立場に立って考える能力は誰でも伸ばせるということに希望がある」という記述に納得できました。

世間と社会
このご本の底に流れている大きなキーワードの一つに「世間と社会」があります。
簡単にまとめると
世間:知っている人とのコミュニティ(相手の立場に立てるし、優しく親切になれる)
社会:世間の周りの人たち(自分には全く関係のない無視しても構わない存在)
と書かれています。
日本人は優しいのか?冷たいのか?は、その人にとって世間の中にいるのか社会の中の人なのかによって、対応が異なるということになります。
自分が知っている人がいる「世間」に属する人に対しては優しく、世間の境界線の外にいる人に対しては冷たい(無視しても良い存在)。
世間が狭いと、自分が関心を持つ人の範囲が狭くなり、ほんの少人数の自分の周りにいる人だけに優しくなります。
この状態が進んでいくと、自分の周り、自分と生活レベルの似ている人たちは世間。それ以外の人は社会の人となり、社会に属する人の立場に立って考えることはしなくてよいことになっていきます。(自分とは関係ない世界にいる人なので)
自分とは環境が異なる生活をしている人のことを自分に置き換えて考えることはしなくてもOK。
多様な人が生きている社会には無関心でOK。となっていきます。
民主主義の基本が、異なる立場の人を思いやり、みんなの幸せを実現することにあるとすると、その前提が崩れてしまいます。
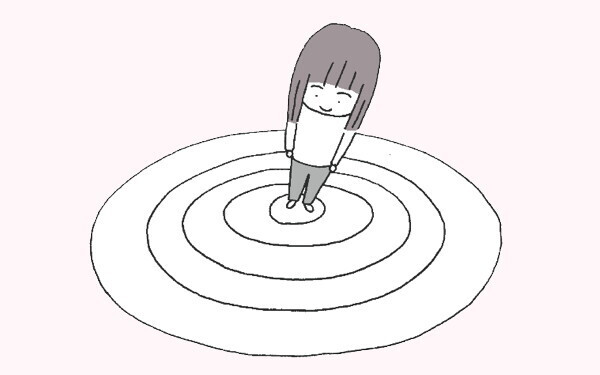
みんなの幸せのために
ここから考えていくと、
自分だけが幸せであれば、他の人はどうでも良い。
しかし、全員がそう考えていると、いつか自分の幸せも崩れてしまう時が来ます。
病気にかからない、勤めている会社は倒産しない・・・自分は失敗しないという保証はないのですから、もしかしたら、自分が関係ないと思っている「社会」の一人になることもありうるのですよね。
そのときにどうするか?を考えてみると、
無関心でいることは自分自身を危険にさらしていることにもなるのかもしれません。
エンパシーを伸ばすことは、自分の身を助けることにもなるのでしょう。
社会の中で困っている人を想像することがはじめの一歩ではないか?と思うのです。
エンパシーは、民主主義や社会主義という考え方を超えて、一人ひとりが幸せに生きるために必要なのだ!と納得できました。
下呂温泉の噴泉池の利用が簡単に!
2021-03-25 | ブログ
先日、緊急事態宣言が解除されてすぐに下呂温泉に行ってきました。
(いろいろなお祝い事をしたくてもできなかったので、まとめて一度に!)
愛知県からさっと行ってさっと帰れる、そして温泉!ということで、久しぶりに下呂温泉に。(https://www.city.gero.lg.jp/kankou/node_7779/node_29737/node_29747/node_32234)
こんなことを考える人たちもやっぱり、ある程度いて…
特に卒業旅行だろうなぁという若者をたくさん見かけました。
きっと、コロナ禍でなければ海外に行ったりしていたんだろうなぁ。そう考えると、日本国内で旅行してくれれば日本経済のためにはプラスかも?
噴泉池の楽しみ
さて、今回、問題意識を持ってでかけたのは、下呂温泉名物の「噴泉池」でした。
飛騨川の河原に源泉が湧き出ていて、そこが無料の温泉で、誰でも24時間いつでも入れる!
温泉に浸かりながら、川面と同じ視線で360度の眺めを楽しむ!
というとっても素敵なスポットです。
20年ほど前に、友人と4人で出かけ(女性は水着の着用OKなので)、水着に着替えて入った!ことがあります。
女性一人では中々勇気が持てず、体験できなかったので、念願の噴泉池体験でした。
その後、下呂に行くたびに噴泉池を眺め、「よしよし。今日もみんなに楽しまれているね」と勝手に喜んでいました。

2007年秋に行ったときの噴泉池のようすです。
災害を超えて
昨年2020年7月に豪雨があり、噴泉池のある飛騨川も被害を受けたとのことを耳にしていたので、現在の様子を確認しよう!という気持ちもありました。(噴泉池、大好きなんだなぁと自分でも呆れつつ)
遠くからみていると、人がいるようなのですがお洋服を着ていて…(あれ?水着の人がいない 💦 きっと、見ているだけなだけなんだよね~)
近づくと…
なんと!足湯に変わっていました(泣)
リニューアルした噴泉池では、多くの若者が足湯を楽しんでいました。
温泉に浸かるよりも、ハードルが低く、たくさんの人に楽しんでもらえるのだということが分かりました。

噴泉池の今。若者が足湯を楽しんでいます。
ということで足湯に変更作戦は、大成功なのかも!と思いました。
SNSが賑わいを創るを実感!
さらに!
下呂のまちを歩いてみると、スウィーツのお店が増えていて、若者がたくさんいました。
インスタ映えするスウィーツで賑わいを取り戻せるんだということを実感しました。
合掌村の近くにある「とちのみせんべい」直売所でも、とちのみモンブランが若者に人気。
下呂のバターを使ったスウィーツ屋さんとか…
まちのあちこちで若者が並ぶお店が見かけられました。
若者の情報収集力におどろきつつ、
「わかもの、よそもの、ばかもの」がまちづくりの要という言葉を実感してきました。
とっても素敵な建物や玄関の旅館が閉まっているのを目にして寂しかったのですが、新しい息吹も感じられて、春が近いことを感じた旅でした。
イベントが成功するには、みんなが力を出し合うこと。
2021-03-17 | ブログ
整備中の公園で市民協働で行う社会実験を行いました。
市民ワークショップから発生した社会実験の試みです。
昨年の12月から話し合いがは始まりました。
そして、月に1回の話し合いから頻度が上がっていき…
3月12日、13日の2日間イベントを行いました。
話し合いが進むにつれて話し合いに参加する市民も徐々に増えていきました。
参加した市民のみなさんの巻き込み力も素晴らしかった!
その話し合いの進行をお手伝いさせていただきました。
イベントは…
公園の一角に花壇をつくり、そこに種を撒いたり花を植えたりするというものです。
先行して大学の研究室が関わってくださった市民農園があり、そこを利用している保育園も参加してくれました。
せっかく参加してくれる子どもたちが楽しんで種を撒くには?
コロナ対応はどうする?
花を植えるデザインは?
などなど、いろいろなことを話し合いました。
イベントだけでなく、花や種に必須の水遣りもみんなで考えるという素晴らしいみなさんです!
自分ごととして捉え、積極的に〇曜日なら水遣りにいけるよ。土日のどちらかならいけるよ。など、面倒なことも積極的に引き受けてくださっています。

みんなで植えたお花です。3種類の花を自分でデザインして植えました。
企画のプロセスは…
全部で13回の話し合いが行われました。
時節柄、リアルで参加できる方、オンラインで参加される方とハイブリッドで行いました。
少しずつ、オンラインの方も増えたので、ファシリテーターだけがオンラインということがなくなり、心強く進めることができました。
やっぱりオンライン参加は複数でないと!
話し合いのプロセスは、5段階となりました。
1.始めは、目的は何か?どんな規模の社会実験をするのか?について話し合いました。
(この時期の話し合いは前に進まず、ぐるぐる迷走状態だったような気がします)
2.次は、新しいメンバーが加わって、リーダーが決まり、日程ややることが決まっていきました。
(リーダーと研究室が支えあって企画書を作成してくれたことが大きく進んだ要因だと思います)
3.こうしたらもっと楽しんでもらえるのでは?こんなことできるよとアイデアや、自分のできることを持ち寄って楽しい企画が加わっていきました。
(ぐんぐんコトが進む時期なのだと思いました)
4.そして、イベントの日にちが近づいてくると、ラストスパート!
きめなく決めなくてはいけないこと、当日のシミュレーションなど事務的な内容を詰めていきました。
(チームとしてまとまっていくという実感が持てる時期でした)
5.当日!
みんなが自主的に参加者が楽しんでくれるように行動をしていました。
(もう、立派にチーム!でした)
成功のポイントは…
ファシリテーターは
はじめは、本当にできるのか?とちょっと不安もありましたが、ファシリテーターが疑いを持ってはいけない!ですよね。
無事にイベントが成功した(完了!)というイメージと覚悟を持って進めました。
チームメンバーは
みなさんが前向きに「やる!」ことを前提に参加してくださったこと。
ご自分のできること(ノウハウや物品、コネクションなど)を積極的に出してくださったこと
公園管理の企業さんが積極的に関与してくださったこと
大学生、大学院生、そして、研究室の先生が推進力になってくださったこと
そして、なにより、みなさんが楽しんで参加してくださったことが大きいと思います。
さらに、
中間で支援してくださる組織の方が、参加される方々への連絡やハイブリッドの場の設定など、細かなところまで支えてくださいました。
ありがとうございました。
市役所の方も、場を貸してくださったり、使用許可など行政の手続きをしてくださいました。
市民と企業・社会福祉法人、行政、中間支援組織などが本当の意味で協働をしたなぁと思います。

規模は小さいイベントでしたが、内容は本当に大きな意義を持った社会実験となりました。
企画側で参加してくださったみなさま、参加者として参加してくださったみなさまのお力です!
感謝しております。
本当にありがとうございました。
ファシリテーターとしても、とても楽しい社会実験でした。
この頃、このパターンでやればよい!というお題は減って、手探りで進めていくということが増えてきました。
参加している方々と一緒に手探りで進むと、チームビルディングにもなり、決定事項には納得感がありました。
協働をすすめていく時代が来た!と思いました。
行動を起こすと何かが変わる!
2021-02-28 | ブログ
Actions are more important than words という言葉があります。これを実感しています。
公園を市民が運営していくことを目指して、ルールや運営づくりに反映させていこうと社会実験を行うことになりました。
まだ、企画の途中ですが…
だんだんと煮詰まってきて、関わっている方々の雰囲気がとても前向きになってきました。(ノッてきた!というか、みなさんの本領発揮!を感じます)
そして、チームビルディングができてきたという実感があります。

すると、先日行った本筋のワークショップもコロナ禍の下ですが、積極的に集まってくださり、とても短時間なのに、濃密な話し合いの内容となりました。
(もちろん、社会実験のミーティングもワークショップもオンラインとリアルのハイブリッド!新しい経験や工夫を重ねさせていただきます。)

何か目標をもって、力を合わせて、コトを企画・実施していく!というのは、その場のもつ空気が変わる!ものだなぁと実感しました。
もともと公園に対する想いを持っているみなさんでしたが、社会実験をすることで公園をもっと愛してくれる人を増やしたい、活用してもらいたい。そのためには、どんなことを、誰に働きかけるとよいのか?をより具体的に考えることができました。
公園を中心にしてまちづくりをする、コミュニティをつくっていく、というのは、こういう具体的なことがあると大きな一歩が進みやすいのですね!
社会実験って、そんな意味もあるんだと体感することができました。
そのレポートは後日。お楽しみに。
*おまけ
オンラインとリアルの会議のハイブリッド。イメージ的には参加者がオンライン、ファシリテーターはリアルの場で!なのですが(というか、そのほうが進めやすい)
社会実験のミーティングでは、ファシリテーターがオンライン、リアル参加のほうが多いという…
当初は、結構たいへんでした。
「もう一度、言ってください」「聞こえませんでした」などと言っていたのですが、
集音マイクを使って聞こえやすくしたり
集音マイクには旗を立てて、こちらを向いて話してねをアピールしたり
オンライン参加者を増やしたり…
と、いろいろと工夫しています。
だんだんと双方とも慣れてきて、ハイブリッド会議でもストレスが減ってきました。
ファシリテーターとしても新しく楽しい経験をさせていただいています。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370