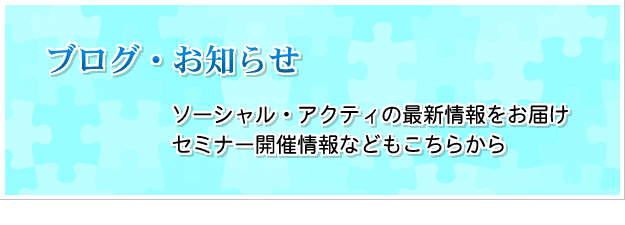
初めての尾瀬!
2024-06-04 | ブログ
群馬県片品村にある「尾瀬国立公園」
小学校の音楽の授業で「夏の思い出」を歌っていた記憶があります。
夏が来れば 思い出す~♬
https://www.youtube.com/watch?v=SS1HhhIWIik
とてものんびりと優雅ささえ感じるメロディ🎵
尾瀬に行くと、水芭蕉がたくさん咲いていて「うわ~きれい!」と思いながらのんびりと木道を散策!
というイメージでした。
 (こんな感じで、おしゃべりしながら、ゆっくりと散策をイメージしていました。)
(こんな感じで、おしゃべりしながら、ゆっくりと散策をイメージしていました。)
履物は連れて行ってくださった方が、スニーカーでもいいけれど、溝の深いものにしてね。できれば登山靴。
とか、傘はあまり役に立たないから、かっぱね。
とか、手袋に日焼け止め、などなど
準備するものを教えていただいていました。
が!
なにせ、🎵夏の思い出🎵のイメージが強くて…
甘く見ておりました💦
ところが、
尾瀬に入山(!)するには、シャトルバスで行く(上自然保護のため)…
そうか、上高地みたいなんだな~と、まだまだ軽く考えておりまして💦
上高地は、大正池あたりから河童橋までは緩やかな登りなので、スニーカーでもOK!
(河童橋からさらに登って明神池まで行こうとするとちょっとキツイですが)
入山していくと、すぐに急な下り。
石の階段というよりも山道…とにかくキツイ
木道になっても、とってもキツクて(木もところどころ腐って穴が開いていたり)気が抜けません。
足元に注意をしていないと、怖くて。周りの景色など見る余裕もなし!
もう、1時間くらい下った気分。

まだまだ急な下りの道なのに、木の根元に水芭蕉が咲いていました。
やっと、水芭蕉が見え始めました。
湿地にあるものだとばかり思いこんでいたので、山道にもあることに驚きました。
休憩所(山小屋)まで降りてきて、やっと休憩。ほっ。
(途中であった方が、山小屋あたりで「早朝、子熊が2頭いたんだよ。気を付けてね」と言われて、熊…いるんだ)
平らな湿原に出たら、もう!水芭蕉が見ごろでした。
頑張った甲斐がありました!
大きなものから、小さなものまで満開でした!
お天気もとてもよく。
天国にきた気分でした。

白い小さな花は全部、水芭蕉!
そして、広い湿地にある木道を黙々と歩き…
どこまでも続く木道と山、青い空。
小さな生き物も発見しつつ、ちょっと苦しくはありましたが、楽しい散策(がんがん歩きましたが)できました。
トイレは100円。
1年間で1000万円も維持にかかるとのこと。
自然を守るため!(PayPayもありました)

木道の木には、「TEPCO 〇〇」の文字がありました。
https://www.tepco.co.jp/rp/oze/mamoru/green-j.html)
お昼は、宿で用意してくださったおにぎりと草餅をいただきました。
とっても、美味しかった。
お昼、場所から少し足を延ばして…
でも、帰り道は、来る時と逆の登り道💦体力をここで使い切ってしまうことはできません!

こんな大きな水芭蕉も!
汗だくで、黙々と上りました。
戻ってきたときの達成感!
元気なうちでないと行けないことを痛感しました。
水芭蕉、2週間くらいが見ごろだそうです。
すごいタイミングで行けたことに感謝。その日に「おいで~」と設定してくださった方に感謝。

汗だくで上っているところを撮影してくださいました。(帽子をかぶっていると暑くて💦)
撮影してくださるなんて、すごい余裕ですっ!
発見もたくさんありました。歌詞に出てくる「浮島」も発見、というか気づきました。終わってみれば、お天気にもお花にも、いろいろな発見!にも恵まれた、とっても素敵な時間でした。
朝のドラマ「寅に翼」の舞台(鶴舞公園)へ
2024-05-22 | ブログ
2024年4月から始まったNHKの朝の連続ドラマ「寅に翼」
日本で初めて女性弁護士になり、戦後初めて女性裁判官になった三淵嘉子さんがモデルになっているとのことです。
明るく前向きに進む寅子に感情移入してしまいます。
初回から欠かさず見てしまいます。
戦前の民法では女性の地位はこんなに低かったのだなぁと思い、
先人の努力で今の女性の地位があったのだと思い、
今はどこまで来たんだろう?と思ったりしつつ。
本当にのめり込んでしまう15分間です。
その中に出てくる「はて?」というフレーズ。これが出ると、ついクスっとしてしまいます。「あ。出るね。」「やっぱり!」と。
このフレーズはファシリテーターとして使える!とも思うのです。
角のない疑問符。
聞こえてきても、心がざわつかないのでは?と感じます。(今度、使ってみよう!)
このドラマによく出てくるのが、
名古屋市にある鶴舞(つるま)公園の噴水と背後にある公会堂。

そして、名古屋市の市政資料館と名古屋市役所。
市政資料館はもともと裁判所でした。ドラマでも裁判所として出てきます。(展示物には、法服もあります)
名古屋市役所(本庁)は、ドラマの大学の廊下として出てきます。

名古屋市役所の廊下。
1階の階段下には、アンモナイトの化石が埋まっています。
よく見かける風景です。
名古屋市にも、まだまだ古い建物が残って(というよりも使用されて)いることが、うれしく思えます。
今、鶴舞公園はバラ園が満開です。
関係ないですが…
バラ園には、「ベルサイユのばら」の登場人物の名前をもったバラがあります。
フェルゼン、マリー・アントワネット、オスカル、アンドレ…
つい、「ベルばら」を思い出してしまうのでした。

マリー・アントワネットというバラ。大輪なのですが、うまく撮れませんでした。
輪島に行ってきました。その2
2024-05-01 | ブログ
輪島にいったのは、4月7日。震災から約3カ月…
東日本大震災(2011年3月11日でした)が起きてから約3か月後に、たまたま釜石に行けるチャンスをいただきました。
なぜか、3か月後…
比較してしまいました。
3か月後の大槌町あたりでは、瓦礫もたくさんあったのですが、片付きつつあると実感しました。

2011年4月大槌町
釜石でも、大槌町でも重機が入って、片付けていました。

2024年4月 大きいものはなかなか片づいていきません。重機が見当たらなくて…
輪島との差を感じずにはいられませんでした。
この理由として、よく聞かれるのは、「能登は半島だから」です。
半島なので、先端までいく道が断たれてしまうとその先、行けない。と言われています。
確かに、今回行った道路をみると、震災前に双方向でいけた能登里山海道は、片道のみ。
崩れてしまった道路は崖のようになっていました。
(下道はどうなっているのでしょう?確認しておけばよかった…)
能登里山海道では、重機も動いていて、道路の復旧を急いでいるんだ!というのは伝わってきました。
この道が通じさえすれば!
重機が被災地に入り、悲しいけれど住めなくなってしまった家を片付ける事ができ、復興に向けて一歩進めるのでは?と思いました。
(輪島まで行けるのに、まだ重機が現地に見当たらなかったことがとても残念でしたので)
重機の操作はできませんが…
出来ること、その1
 (https://www.nitech.ac.jp/news/news/2023/10871.html)
(https://www.nitech.ac.jp/news/news/2023/10871.html)
お世話になっている名古屋工業大学に、建築の北川先生がいらっしゃいます。
先生が開発された「段ボールハウス」が避難所で活躍しているそうです。
ちゃんと個別のスペースができ、保温もでき、組み立てが簡単!
名古屋工業大学では寄付を募っています(もちろん、使途を指定できます)。
で、段ボールハウス1軒分ですが…
気持ちを託しました。
お申込みはこちらへ(https://www.nitech.ac.jp/kikin/donate/index.html)
名古屋工業大学のキャンパス内に北川先生のオフィスになっている「ゲル(と呼んでいます)」があります。
一度、これはなんだろう?とうろうろ見ていた時に、ばったり北川先生に会い、
中に入れていただきつつ、丁寧にご説明をしていただいたことがあります。
プラスチックを吹き付けただけ(?)という簡単な工法らしいのですが、中はとっても快適!
これが、被災地のあちこちに設置されていました。

この白いゲル風の建物(と呼んでいいのか?)が走っていると散見できました。
より、寄付しなくては!と思えます。
出来ること、その2
私の所属するNPO日本ファシリテーション協会(FAJ)では、3.11直後にA4用紙、プロッキー、養生テープを車に積み込んで被災地へ行く!という活動を始めた仲間がいます。
避難所でのミーティング、多様な立場の人たちの様々なミーティングの議事録などなど、ファシリテーションのスキルがお役に立つことはたくさんあったようです。
今でも災害のたびに、グッズを持って被災地へ!
メンバーとして誇らしく、頭のさがる活動です。
(プロッキー、とっても使い易いので、お薦めです)
ボランティアでお片付け!は、私が被災者だったとしたら、直接お役にたつ!と思うのですが、
体力に自信がなくなっていくお年頃としては、勇気がでません。
普段から、できること、必要なことをやろう!と思うと、できることは…
ファシリテーションのスキルをbブラッシュアップすること、みなさんに知っていただくことでは?と思います。
という訳で、これからも、ファシリテーションのスキルを磨いていこう!
みなさんに知っていただこう!と心に決めたのでした。
輪島に行ってきました。その1
2024-04-11 | ブログ
4月7日(日)に輪島へ行ってきました。今回は「その1」のご報告です。
もともと現地に不案内、そして、道路にどのような地震の被害があるのか?よく分からないので、タクシーをお願いしました。
のと里山海道という高速道路が輪島まで通っているそうです。行は金沢から輪島までこの道路を通れるようになっています。帰りはその道路が通れなくなってしまっていて、途中の徳田大津ICから乗れるということで、輪島から徳田大津までは下道を通って帰ることになります。
早朝に金沢を出発したので、行も帰りも順調にスイスイと行けました。
もう少し遅く出発していたら、帰りは渋滞していたとのことでした。(早起きは3文のトク!)
のと里山海道は、穴水あたりから亀裂やがけ崩れがありました。
道路の亀裂は、ずいぶん改善されていて段差が修繕されていました。
ただ、海側の車線や盛り土の車線は崩れてしまっているところもあり、復旧はたいへんだろうなぁと素人でも分かる状態でした。

色の違っている部分は生じた亀裂を修繕したところです。
被災地へ向かうための道路の確保は大事だなぁと思いました。
もちろん、電気・上下水道が整うことは必須だと思いますが、そのための資材を運ぶにしても道路がないと直しに行けませんもんね。

朝市の通り。3か月たったのに。
輪島の朝市通り
なかなか瓦礫の撤去が進まないと言われていますが、分かりやすいと言われている輪島の朝市通りやキリコ会館などに行きました。
朝市通りは火事も起こったらしく、車が錆びてしまい、そのままになっていたり、家から出た震災ごみ(というのも申し訳ない気持ちですが)が玄関先に置かれていたりするのを見ました。
生活道路のような道なので道幅が広くはない所に、ゴミが出されていて、車が通りにくい状況になっているのも見かけました。

朝市の通り。3か月たったのに…
順調に片づけていらっしゃるのだなと思うと同時に、スピードが気になりました。
3.11のとき、同じ3カ月後の6月に釜石へ行ったのですが、その時と比べると、やはり片付くのが遅いのでは?と思いました。
もし、自分が被災したと思うと、茫然としてしまって生活を再建するというイメージが湧かないかも。
そして、いつまでも被災した時の状態のままになっていると、だんだんと再建しようという気持ちが無くなっていってしまうのでは?
と思いました。
前向きになるためには、何かの踏ん切りがつくようなことが必要で、それは、私だったら家を片付けるというのが大きい要素になるような気がします。勝手な想像なのですが…
まだ生活感が残っていた場所でしたので、なんとも言えない気持ちになりました。
キリコ会館あたり
輪島は北前船の能登半島の拠点で栄えた地域だったとのことです。
輪島塗の文化が代表するように商家も豊かな豪商が多かったのでは?と想像できます。
https://www.kitamae-bune.com/travel/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E8%BC%AA%E5%B3%B6%E5%B8%82/
豊かな能登・輪島では、キリコ祭りというお祭りがあるそうです。キリコは山車(だし)だそうです。
キリコとは、輪島では「キリコとは、切子きりこ灯篭を縮めた呼び名であり、直方体の形をした山車だしの一種で、担ぎ棒が組み付けられている。」出典、写真も https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story004/#:~:text=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%87%E5%AD%90%E3%81%8D%E3%82%8A%E3%81%93,%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

キリコ祭りも毎年行われているとのことです。
地区同士でキリコを競い合ってつくっていた(そのくらい豊かな地域!)とのことで、壮大なキリコの様子を思い浮かべました。
このキリコが展示してあった「輪島キリコ会館」は2024年4月7日現在、休館していました。
キリコ会館は海沿いにあり、地面が割れ、段差ができていました。さらに、液状化もあったようで、地面がうねっているところもありました。

海岸沿いの遊歩道。分かりづらいですが、段差が10㎝以上できてしまった場所もありました。電柱も斜めになってしまっていました。
そのすぐ近くに仮設住宅ができていました。
ちょっと安心できる場面でした。

たぶん、仮設住宅
仮設住宅の近くになった新築の家は無事!のようでした。
耐震というのは、本当に大切なのだと思いました。(我が家の耐震化は大丈夫?と確認してしまいました)
今回は、タクシーの運転手さんが、何度もお仕事やプライベートでも来ていた能登ということで、いろいろなお話を聞きながらめぐることができました。
土地勘もなかったので、とっても助かりました。
情報量がありすぎて、まだ整理できていません。なんとか、忘れないうちに整理しておきたいと思いました。
また、このページでお知らせできれば…と思います。
今回の視察を何かに活かしていきたいと思いました。
でないと、被災したみなさん、地域に申し訳ない気がしています。
3.11の後、防災に対する気持ちが強くなり、ファシリテーションを活用して、防災のワークショップを企画したり、
どう分かりやすく伝えていけるのか?を自分なりに継続してきました。
今後も、私にできることは何だろう?私たちにできることは?を考えて行動していきたい!と思いました。
福島県浪江町に行ってきました~その2ワールドカフェ
2024-03-29 | ブログ
福島県浪江町のご報告、その2です。
今度はワールドカフェ。浪江町とワールドカフェのつながり…
見えてきました?
さて!今回の大きな目的の一つは、浪江町の職員の方に会うことでした。
浪江町は駅前にF-REI(エフレイ)福島国際研究教育機構を誘致します。
https://www.f-rei.go.jp/

(もう、既に、一部研究者も入ってきているそうです)
この誘致は復興の目玉にもなります。
F-REI、国際的な研究機関がまちにやってくる!ってとっても誇らしいことのような気がします。
愛知県岡崎市にも研究機関があり、地元では、「分子研」と呼んでいます。
正式名は、大学共同利用機関法人、自然科学研究機構 分子科学研究所 です。https://www.ims.ac.jp/
国際的な研究機関らしいのですが、子ども向けに科学のイベントをしてくださったり、地域の人に中をオープンにしてくださる時があったりと地域との接点を持つようにしています。
なんとなく、そのような研究機関が地元にある!というのは、海外からのお客さまも多くて、案外国際都市では?と思ったり、自分も賢くなったような(全く関係ないですが…)気がしたりします。
浪江町の人もきっと同じ様な気もちになる方もいらっしゃるのでは?
そして、心の復興のシンボルになるのかもしれないなぁと思いました。
ワールドカフェで!
F-REIと周辺地域が一体となって町ができていくように、F- REI門前町の価値向上・魅力向上勉強会(全4回)とF‐REIの立地を踏まえた浪江町の未来を考える住民ワークショップ(全2回)が行われました。
これらが、なんと、ワールドカフェで行ったとのことなのです!
たしか昨年の4月あたりに、オンラインでワールドカフェの進め方を職員の方にお伝えしたのでした。
ワールドカフェを体験したことがない職員の方が、話を聞いて、イメージして開催してくださいました!
今回、役場をお尋ねして、直接お目にかかり、ニュースレターや報告書を拝見しました。
写真を拝見しても、和やかな雰囲気の中で、楽しく対話できたんだろうなぁというのが伝わってきました。
もう、職員のみなさん、ワールドカフェ マイスターです!
すごい能力とスキルです!
お二人とお話をしたのですが、メンバーチェンジすることがいいなとおっしゃっていました。
いろいろな人と対話をすると、いろいろな立場、考え方も分かるので、話し合いが和やかで一体感が出てくるとのこと。
一体感があると「みんなが幸せになるには?」を考えやすいのでは?と思いました。
参加した方の中で、ワールドカフェでの勉強会の雰囲気を伝えてくれる投稿がありました。
https://satellite.net.fukushima-u.ac.jp/news/202311013186
ここにも、「和やかな雰囲気の中」とありました。
(なぜか、私もうれしくなってしまいます)
参加した方々が、もっと浪江町が好きになって、もっと積極的にまちづくりに関わってくださるようになることをお祈りします!
震災、放射線の被害からの復興にも、ワールドカフェがお役にたつなんて、
ワールドカフェ好きな私としては、とってもうれしくて、光栄です。
対話しよう!
今、対話の時代と言われています。
暉峻淑子『対話する社会へ』とか、昨日読了した神野直彦『財政と民主主義』にも書かれていました。様々な書籍に書かれていますよね。
そうそう、デビッド・ボウム『dialog』もありました(これは、対話の意義が分かる、ある意味、バイブル(笑))
その対話の進め方の一つがワールドカフェです。
パターンが決まっているので、進め方は簡単。
そこに、いろいろな工夫をします。
その場にいる人たちがお互いに刺激しあって、話し合う。未来を考え、言語化する。
とっても素敵な空間であり、時間になります。
お互いの存在を認めあう空間であり、時間なのだと思います。
対話の後、満ち足りた気持ちになること、ありますよね。
勝手に対話の効果を考えると、お互いの存在を認めあう「承認欲求が満たされる」ことがあるのでは?と思いました。
(『財政と民主主義』にも、これからは所有欲求ではなく、存在を認められる欲求を満たすことが求められるとありました)
これから、もっと対話が求められるようになりそうです。
もっと、ワールドカフェのファシリテータ―のスキルを磨こう!と思いました。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370


