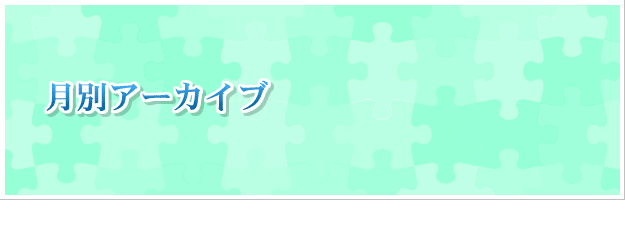
久しぶりにOka-bizセミナーに参加しました
2023-10-26 | ブログ
岡崎市にある(誇る)Oka-biz(岡崎ビジネスサポートセンター):https://www.oka-biz.net/
いろいろな講師を招いてセミナーをしてくださっています。
地元のビジネスパーソンたちが元気になるような内容を提供してくださっています。
(そして、無料!←これ、すごいことですよね)
10月24日のセミナーに参加してきました。(とっても久しぶり)
タイトルは「小さな企業の生き残り戦略」
ゲストは、豪華に3人!
(株)エニシングの西村氏、(有)片岡屏風店の片岡氏、中小企業を応援する雑誌リファラバの清水氏
そして、ホストはチーフコーディネーターの秋元氏
ゲストの会社は
エニシングさんは、前掛けを製造販売しています。そして、西村さんはスタートアップ!起業されたのです。
エニシングさん:https://www.anything.ne.jp/index.html
西村さんの記事:https://www.recruit.co.jp/blog/guesttalk/20220105_3003.html
 (エニシングさんのHPより The まえかけ!これこれ。懐かしいです~)
(エニシングさんのHPより The まえかけ!これこれ。懐かしいです~)
ちょっと考えると、伝統的な前掛けで起業?なんだかヘンな??
思うのですが、製造は職人さん、販売はエニシングさんとなっているようです。
前掛けは昭和40年代が生産のピークで、年間200~400万枚生産されていたそうです。
2004年には前掛けの関連会社は10社しか残っていなかったとのことでした。
そして、前掛けの主な生産地は愛知県の三河地域!
(そういえば、三河木綿ってこういうゴツイ感じでした。三河木綿と言えば、ガチャマンと呼ばれていた時代がありました。戦後の物資がない時に機織り機を一回ガチャンと回せば、当時で1万円が入ってくるという信じられないような黄金時代)
そして、前掛けは、BtoBのプレミア商品として生産されていたらしいのです。
アメリカの前掛け展示会に豊橋の職人さんを連れていったときに、職人さんが「前掛けにお金を払っているのを初めて見た」と言ったそうです。
まさに、BtoB!
相手をBからCに変えたところが成功のカギだったようです。今では、海外からのオーダーが多いとのことでした。
片岡屏風店のほうは、片岡さんは屏風3代め。
片岡屏風店:https://www.byoubu.co.jp/
古くから活用されてきたのが屏風!平安時代の源氏物語が描かれているもの、時代劇に出てくるもの。
いろいろな場面で日本人の生活に使われていました。(そういえば…我が家にも、以前ありました。随分古びてセピア色になってしまっていましたが、祖母の部屋にあった記憶があります。とっても便利に使っていました。)
片岡さんのところは、主に人形を飾るときの屏風だったそうです。
2代目のときに、ホテルなどにある金屏風を製作しはじめたとのことです。
(↑特におめでたい記者会見のときは、見かけますよね)
屏風も伝統産業。今では、なかなか普段の生活で見かけることはないですよね…
そして、たぶん、こちらのお仕事もBtoB
片岡さんもスウェーデンでの展示会からはじまって、海外展開していらっしゃるとのことでした。
こちらも、海外からのオーダーが多いとか。そして、既成観念にとらわれない発想でつかわれているらしいです。
そして、リファラバの清水氏
リファラバ:https://refalover-note.mainichi.jp/n/n93cb4296cc0a
 (リファラバHPより)
(リファラバHPより)
リファラバは、「毎日新聞がファミリービジネス・メディアを始めます。孤独な経営者や後継ぎ、起業家を「つなぐ場」になります」と立ち上げられました。
このトップが清水氏。
毎日新聞の記者で、金融畑を歩んでいらして、ワシントンへも赴任していたそうです。
そんな経緯の中で、中小企業が日本を支えているというのを感じ、中小企業の自由な発想も好きで、立ち上げたのだとか。
(みんながみんな、大企業にお勤めしているわけではないですものね)
上のお二方は、リファラバでも掲載されたとのことでした。
みなさんのお話の共通点は、
3人ともアメリカに留学、または赴任していたことでした。
ここから、日本という国、日本の文化などなどを外から見ることができ、伝統を見直し、マネタイズすることができている。
(というところまで、伝統を昇華させている と言ってもいいのかもしれません)
今回のお話の中で、( ..)φメモメモしたのは…
・徹底的に観察・分析。そして気づくこと
・その気づきをカタチにすること
・視点を広くして(競争がない場所へ)行く
ということでした。
「めんどくさい」に拘るのも大切みたいです。
という事は…
自分に問いかけてみると
固定観念ができてしまっていないか?
(自分で自分の枠を決めてしまっていないか?)
でした。
お仕事をいただくときも、仕事を進めていくときも!
常に新しいものやことに目を向けてしっかりと観る。ということを心がけていこう!
と思いました。
ふぁ~っと目の前が開いていくような気がしました。
刺激を受けるのって、大切ですね!
Oka-Bizさんに感謝です。
あ!この考え方は、商店街にも通じそうです!ヒントいただきました~
高齢化すると医療の充実が求められるんですね
2023-10-13 | ブログ
先日、友人の別荘にお邪魔してきました。
平野と比べると、とっても涼しい(行ったときは10月に入ってすぐでした。朝晩は肌寒いくらい)気温でした。
湖や遊歩道も近く、初めてのSUP(stand up paddle)に挑戦したり、お散歩したり、
地元の野菜や栗を堪能したり、
そして、なにより、友人たちとの楽しい時間を過ごしてきました。

初めてSUPしました。
案外、いける!とうれしかったです。
ご近所の方にもばったり!で、コミュニティになっているんだなぁと思いました。
普段の住まいの方が被災しても、こちらにくればOK!とのこと。
←なるほど。そういう備えというのもあるのですね~

紅葉にはまだ早かったのですが、美しい景色の中に浸かっていることができました。
今回は、ご両親の話題から…
お父様は持病をお持ちの様で、お散歩がちょっと辛い場所があったようで、足腰を大切にしていらっしゃいました。
もう、リタイアしてらっしゃるので、別荘を終の棲家としてもいいのでは?とお聞きしてみたところ…
普段は今までのご自宅にいらして、土日に別荘にいらっしゃるのだとか。
その一番の理由が、お父様の通院とのことでした。
きれいな空気、きれいな景色、おいしい地の物…
たくさん魅力的なコンテンツがあるのに、なぜ、2拠点生活?
特に夏は、山の上のほうが涼しいですもんね。
この夏、伊豆高原に行ったとき、別荘地の中をタクシーの運転手さんのお話によると…
「一時は、別荘地もいっぱいだったんだけどね。医療が充実てないから、ここに住めなくなるんだ」
でした。
リタイアして、やっと別荘でのんびりした生活を!と思った頃には、
別荘での暮らしがキツイものになってきてしまうようです。

この駅から少し登っていくと、別荘地があります。
これらのことから、別荘ってステキ!と思っていたのですが、案外難しいことがあるのだなと思ったのです。
友人の別荘近くの遊歩道がある場所には、平坦な場所があり、そこは、ドクターヘリが着地できるようになっていました。
なので、緊急のときは、安心。
中山間地域に住むということ
夏の伊豆高原、今回の高原から類推すると…
今、移住を促進させる、定住を増やすという政策が行われています。
地域おこし協力隊というのも、その一つですよね。
でも、日本の中山間地域は、医療が充実していないと耳にします。
テレビドラマで、「はやぶさ消防団」というのをやっていました。
若い東京のミステリー作家が実家である、中山間地域のはやぶさ地区に(戻るというよりは)移住してくる物語です。
この中でも、もともと住んでいる高齢の方々は、病院へは山を越えて通院していました。
通院は一日仕事です。

日常的に医療が必要なおとしごろになると、その充実が気になります。
もしかしたら、一旦移住しても、高齢になってくると都会へUターン!ということもあるのかもしれません。
「まち」と言われていても、だんだんクリニックが減ってきている、身近な病院が(赤字で)減ってきている…
という話も聞きます。
病院も一極集中が進んでいるのかもしれません。
なかなか、個人レベルで解決できることではないですが、今後、どんな方法があるのか?についてもアンテナを張っていたいなと思いました。
ニュースレター第145号「参加型トークイベントをファシリテート」
2023-10-04 | ニュースレター
先日、中心市街地活性化のビジョンを作成するキックオフとして、トークイベントがありました。
そのイベントでファシリテーターを務めました。
進行はもちろん、参加型で!
イベント終了後に、参加した方に声をかけてもらったり、片づけを手伝ってくださったり…
ファシリテータ―としても、とても、うれしい!を実感したイベントになりました。
ニュースレター第145号「参加型トークイベントをファシリテート」ご覧ください。


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370




