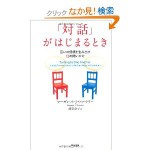まちの問題、企業の問題3
2014-06-09 | ブログ
今回のテーマは「電気自動車ベンチャーの軌跡 ~日本最後の自動車メーカー(株)ゼロスポーツ創立者の挑戦~」
というものでした。
元(株)ゼロスポーツ社長、現在はGlobal Mobility Sernice(株)の代表取締役をしていらっしゃる中島徳至さんがお越しくださいました。
いつも、起業家を呼んで講演会をしてくださるOka=Bizさんには感謝です。
どんな会社?
今から23年ほど前に会社を興し、自動車用部品開発をしてこられた中島さん。はじめから電気自動車を作って売りたかったとのことでした。ただ、その道はあまりにも遠いので、(既に自動車メーカーは日本国内にも数々ありますので、今から参入?という茨の道です)部品で始めて資金を増やして行こうという遠大な作戦だったとか。
日々の営業と商品開発の努力の賜物と(私は)思うのですが、富士重工さんの目にとまり、純正品メーカーにまでなりました。これだけでも素晴らしいです。
その後、いよいよ電気自動車を開発し、売りだす!過程に入りました。
なんと!日本郵便さんから1000台を超えるオーダーがはいったのだとか!
そのオーダーをこなすためのバリューチェーンも構築し、いよいよ!というときにまさかのキャンセル。そんなことって???
そして、会社を清算することにし、債権者集会も全て出席し、債権者に事情の説明をして回ったそうです。
その態度が好感をもたれ、ましてやゼロスポーツさんの落ち度でもなく・・・メインバンク(どこなのか教えてはくださいませんでしたが)以外の銀行さんは応援してくださったということでした。
20年続いた会社は、こうやって消滅してしまったのです。
そして、今はご縁があってフィリピンに工場を置く現在の会社の代表取締役になったそうです。
熱い想いは!
1時間ほどのお話を聴いていて感じたのは、心の底から現在の化石燃料を使う生活の未来はないと確信し、新しいエネルギーで生活をしていかなくてはならない!そのためには電気自動車なのだ!と考えて行動していらっしゃるのだなぁということでした。
とんでもないような経験をさせられてもなお、日本の、地球の未来を考えて行動していく、そんな強い意志を持った方でした。
熱い想いと強い意志が伝わってきました。
その熱い想いは、人間の生活が成り立っていけるよう、サスティナブルな世界をつくっていくことで、そのためには、車の燃料はガソリンではなく電気なのだという揺るがない考えからきているのです。
企業として活動すること=まちづくり(というよりも地球をつくっていく?)ことになるのだと思いました。
まちの問題と企業の問題
起業家の方々のお話を聴いていると、みなさんアプローチは違っても、会社として業を興し、発展することが世界を人類を地球を救うことになる!と確信し、日々努力していらっしゃるといういことが分かりました。
このくくり方を変えると、まちづくりといわれる分野なのだなぁと改めて考えました。
まちづくりといわれる分野も、人々が幸せに生きるためにどうするのか?なにができるのか?から出発しています。
そういえば、松下幸之助さんだって、豊田喜一郎さんだって、この製品をつくって何をしたかったのか?というえば、お金を儲けたいと思ったのではなく、みんなの幸せのためになる!と信じてその道をわき目もふらずに歩いていらしたのでした。
創業者=起業家は、世のため人のために努力しているのですね!
それはまちの問題だから、企業で働いている私たちには関係ないよ。とか、これは我が社のソーシャル・ビジネスの担当?CSRの課題?だね。とかいうすみ分け(?)のようなものでは、もともとはなかったのですね。企業の活動そのものが、、まちの課題を解決したり、まちをつくっていくということだったのです。
対話はくっつける作用がある
このごろ増えてきた、また私がつくりたい!と思っているフューチャーセンターは、対話を中心にしています。いろいろなステークホルダーが集まって、課題をだしあったり、話をしたりする中でお互いの課題を解決していきます。多様な参加者がいれば、多様な視点から課題を見ることができ、解決策も出てきます。
そして、立場の違いを超えてアイディアや人々の心がくっついていくのです。
対話によって分断された人々の心がくっつくというのは、『対話』という本を書いた、物理学者で哲学者のデビット・ボウムも言っています。科学的な思考法が人々を分断してきたのだと。だから、今、孤独や孤立といったことが社会問題になるほど大きくなってきたのです。
ここで、もう一度分断されてしまった心やつながりをくっつけることが必要なのです。
子どもたちやその子ども、またその子どもたちに「ステキな未来を描くこと」ができるようにしておくことが、今大人でいる私たちの務めなのですね。きっと。
そんなことを考えた講演会でした。
今、対話したいとき! ~FAJ定例会から~
2014-05-21 | ブログ
対話の定例会
5月のFAJ(日本ファシリテーション協会)中部支部の定例会を担当しました。
テーマは「あえて今、原点に戻って Facilitators’ Dialogue2 ~本気でじっくりファシリテーションを語り合おう~」にしました。そのものズバリ!なテーマでしたが、定員30名のところ、28名も参加表明があり、担当者としては意外に多くて驚きました。
いつも、2テーマ開催しており、今回の表のテーマは「アイスブレイク」でしたので、楽しそうで役立つアイスブレイク研究に人が集まりそうでした。あえて裏番組的に小規模で開催しました。
対話のイメージは・・・ アイスブレイクに比べて暗い・地味。4時間も何話すの?せっかくの定例会なのに得るものはあるの?などなど担当者ながらネガティブなイメージを持つよね~と呟きながら・・・
でも!対話は大事。今、あえて対話しておきたい! ファシリテーションについてみんなの想いや願いなどじっくり話してみたい!という想いをもって始めました。
対話のプロセス
① 全員でチェックイン 一人ずつフリップを作って自己紹介
② 4人グループになって一つめの問い「あなたにとってファシリテーションとはなんですか?」
③ メンバーを変えて、同じテーマでもう一度。
④ ③と同じメンバーで、「あなたはファシリテーションで何を実現したいのでしょう?誰と、どんなことを?
⑤ メンバーを変えて、同じテーマでもう一度。
⑥ ⑤と同じメンバーで、もう一度「あなたにとってファシリテーションとはなんですか?」
⑦ ハーベスト (写真をご覧ください)
こんな風に進めました。
感想は
・ ダイアローグを通じて参加者(の一人)が変化していくのを実感した。モヤモヤはまだ残っているが、家に帰ったら娘との関係を見える化する、向き合う勇気を持つことをやってみたい。
・ ファシリテーションは万能の魔法ではない。一つの手段に過ぎない、ということを理解した。
・ どうしてファシリテーションを勉強したかったのか、何をしたかったのか、思い返す1日だった。前向きになることができた。
・ 元気になった。この場にいることでストレートに元気をもらうことができた。
・ テーマが良かったので絶対参加したいと思っていた。みんなの思いを教えてもらい勉強になった。たくさんの人の話を聞きたかった。予想外のハーベストタイムでワークショップの楽しさを感じることができた。
・ 初めて参加した。まだファシリテーションをよく理解していないが、直接話を聞くことができた。「ファシリテーション」というテーマだけでこれだけ話せるんだと驚いた。
・ 最後に輪になっての表現は良かった。個人個人を尊重すること、これが結論となった。
などなど、もっとたくさんの感想がありましたが、このくらいにしておきますね。
そして、そのときの私の感想は「振り返りの言葉を聞いて、今日の話し合いが一人一人の心の中に染み込んでいったことがわかった。この場にいられてうれしい。」でした。
対話をして、自分と違う人の考え方があることを実感したり、元気に前向きになったりした方が多かったようです。「そもそも」の原点を話し合うことは、自分の中にちゃんと落ちて、明日への活力になるのですね。自分が何をしたかったのか、なぜこうしているのか・・・
自分という存在の意味を再認識できることで、前向きになれるのかもしれません。
今、『対話がはじまるとき』
ワールドカフェを創った一人にマーガレット・J・ウィートリーという経営コンサルタントの女性がいます。彼女の著書『「対話」がはじまるとき』には、なぜ今、ワールドカフェに代表される対話が広がっているのかの秘密が書いてあります。
それは
・未来への希望を取り戻すこと
・世界を変えることができること
ということらしいのです。未来を、世界を変えるパワーが対話にはあるというのです。『Dialogue』を書いた物理学者で哲学者のデビット・ボウムも言葉を変えて同じことを言っています。
人々がの心が分断されてしまっている現在、その破片を拾い集めてくっつけることは可能で、それは対話によるというのです。壊れてしまった花瓶はくっつけても以前の機能は取り戻せませんが、人の心は修復可能なのです。
心がばらばらになっているから起こる孤独や孤立・虚無感、攻撃的になると排除となり、それが集団の間で起きてくると紛争に発展してしまうのです。心と心がくっついてつながっていれば、心は穏やかになり、争うことをしなくてもちゃんと満たされているのです。孤独や虚無感はなくなり、紛争も必要ありません。
というようなことが書かれています。
このような力があれば、未来への希望も取り戻せるかもしれません。未来への希望があれば、小さな力が集まれば世界を変えることができるかもしれません。そんな希望が対話には潜んでいたのですね。
だから、定例会の感想にも、人とつながってみる勇気がもてた、他の人と共有できた喜び、前向きになれたという感想が多くあったのですね!
おわりに
遠大なお話になってしまいましたが、今回の定例会でも、参加した方々の感想から、対話の本質を感じて下さった方がたくさんいらっしゃいました。ファシリテーターができることは、まず、このような場で、質の良い対話の時間となるよう努めることからはじまっていくのかなと思っています。
FAJのメンバーは、質の良い話し合い・質の良い対話を経験している人々が多いので、その方々が広めていく中心にいたら、ステキだなと思います。
もちろん、FAJのメンバーになっていなくても、そのような場を提供できるかたはたくさんいらっしゃいます。そんな方々とも心をくっつけて行けたら、もっと大きな広がりになっていくのでは?と期待しています。
もちろん、私自身も傍観者ではなく、自ら行動していきたい!と思います。
地縁団体について考える2 ~町費の徴収について~
2014-04-29 | ブログ
前回は町内会の法人化についてご報告しました。
今回は法人化の有無は別として、町内会の会員から集めた会費である「町費」の徴収方法について、裁判所の判断がありました。平成14年の判決ですが、こちらも備忘録としてメモしておきます。
町費の使途について
町費は月にいくら、年でいくらと町内会ごとに決められています。私の住む町内会では組長が一年に一度、各世帯を回って集金し、町内会長(総代)宅へ持参し、まとめられた町費を会計さんのところへ持っていきます。会計さんが銀行へ入金する。という手順です。
この町費の運用は、総会で承認された予算に従って執行されていきます。この支出の中には、子ども会への助成やPTAへの助成、町内の資産(公民館など)の運営に充てられるものもあります。
そして、従来であれば何の躊躇もなく、(地縁団体について考える1のような経緯があり)神社や墓地を守っている寺院などにも支出されていました。ところが神社等への支出を前提とする町費の徴収については、信教の自由を侵害しているとの判決がおりていたのです。
支出が違法というのではなく、違法な徴収方法だった、ということでした。
そうでした。町内会は任意団体でした。前回の「地縁団体について考える1」でも公法人とはいえ、法人は公益財団法人や会社などに比べるとイレギュラーな存在です。
判決の内容は?
その判決は、平成14年4月12日、佐賀地裁でありました。
ざっとした内容は、「集めた町費から宗教法人である(氏神さまですが)神社関係費の支払いを拒んだ町内会会員に対して、町内会会員の取り扱いをしないとの判断をした町内会の行為は、神社神道を信仰していない町内会会員の信教の自由を侵害しており、違法であるので、町内会会員の地位確認請求が認められました。ただし、町内会の不法行為による慰謝料請求は棄却されました。」というものでした。
なんだか分かりづらいのですが、
集めた町費の中から、勝手に宗教団体である氏神さまに関係する費用を支出するのは、氏神信仰をしていない(もっといえば、氏神信仰を認めていない宗教を信仰している)町内会会員も、氏神さまを無理やりに信仰をさせられているということになる!
そのことを申し出たところ、町内会から脱退してくれと言われた。これは強制ではないのか?信教の自由を侵している行為ではないのか?自分の払った町費から神社のために支出をしなくても町内会会員として認めてほしい!
裁判所に訴えるにはお金に換算しなくてはいけないので、慰謝料を請求する、ということにします。
というようなことのようです。
(1)争点は?
この判決の争点は、①町費の徴収方法自体についての適否、②原告が町内会の構成員という地位を有しているのか、③不法行為が成立するのかの3点でした。
①町費の徴収方法については
一般会計と神社関係費を区別せずに徴収したことは違法としています。
→区別しなくてはいけないということですね?または、集金時や総会などで確認するということになるのでしょうか?
②原告の町内会での地位は
もちろん、判決では、「町内会の構成員」。使途に対する考え方が違うと言って、町内会の構成員からはずす!のは認められないちうことですね。
③不法行為については
慣習に従って徴収していたこと、原告の指摘後は改善しようとの試みがあったことなどを考慮して、「故意、過失」がなかったとして違法性はなかったということになっています。
(2)前提:氏神さまは宗教なのか?
氏神さまは宗教団体といえるのか?という問題があります。この判決では、
信教の自由と政教分離を定めた憲法第20条1項、後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。」
公の財産の支出または利用の制限について規定している憲法第89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
でいう「宗教団体」あたるとしています。
なので、信教の自由を侵害していると。
*参考文献 小倉一志「公報判例研究」『北海道大学論集、54(4)』
神社等と町内会の関係は?
神社について、
権藤成卿によると、律令制前の日本では、社稷(しゃしょく)という考え方があったそうです。社(しゃ)は土地の神、稷(しょく)は穀物の神をあらわしていて、それぞれの土地でそれぞれの穀物を尊ぶという氏神様の考えで、この考え方から「共同体」が生まれてくるとのことです。(佐藤優『宗教サバイバル』より)
また、中川剛『日本人の憲法感覚』では、日本のコミュニティと神社は本来深く結びついていて「社」の字は祭壇に土を合わせて成立していて、それ自体で土地の神を示すものになっているとされています。そして、地域社会が神社を維持することは、社会の統合をはかるためであって、信仰を強制することとは無縁である、ともいわれています。
しかし、法的には、この判決のように捉えるのが法理論に適っているようです。
明治維新によって、もともと峻別されていなかった神社と寺院が明治政府の廃仏毀釈政策によって無理やり分けられ、戦後、氏神さまを国家神道の反省から宗教法人としたことから、このような複雑なことになってきたような気がします。
コミュニティが衰退している現在、神社の行事である祭りはコミュニティの人々がアイデンティティをもてる貴重な機会となっています。祭りの復活も聞かれます。ニュータウンでは、中心となる神社がないので、○○祭りとして新たな機会を作っています。子どもたちもお祭りは楽しみにして、この町の一員なんだなぁと感じるときなのではないかと思います。
そのことと、断りもなく町費から神社の費用を支出してもよいということはイコールではないかもしれません。ただ、コミュニティの視点からすると、律令制の前から連綿と続いてきて、コミュニティの中心となってまとめてきた神社を宗教法人としてドライに割り切れないものを感じます。その歴史をふりかえって、もう一度捉えなおすということは難しいのでしょうか?
地縁団体について考える1 ~法人化~
2014-04-23 | ブログ
新年度に入り、町内会について考える機会がありました。地縁団体について以前調べたことと併せて備忘録として書きとめておきます。
まずは、認可地縁団体について
地縁団体の法人化
1991年4月の地方自治法の改正(第260条の2)によって、自治会・町内会は法人となることができるようになりました。
町内会の人々がお金を出し合って造った公民館や代々の墓地や神社の祠などは町内会として持つことができるようになったのです。ただし、法人としての権利が主張できるのは、町内会で不動産を所有するためだけであって、その他の契約行為などの法的な主体にはなれません。
申請は基礎的自治体の長の認可でこと足ります。法務局で法人登記をすることはしなくて良いようです。
その背景は、戦後から地方自治法の改正までは、登記上は代表者の所有ということにしておいて、実際には町内会全体の所有という一つの不動産に対して法律と実態の差がありました。「町内会所有の土地をとりあえず、町内会の代表の持ちものとしておこう」として登記してあったところがありました。すると、その代表が亡くなると、子どもがその土地の相続をすることになります。町内会のものだったのが、いつの間にやら個人のものになってしまっていたのです。そこで、子どもに事情を理解してもらい、もともとの町内に戻そうとすると、子どもに相続放棄をしてもらったり、所有権移転をしてもらったりと、非常に煩雑な手続きをしなくてはなりません。また、子どもが全国に散らばってしまっていたり、亡くなって相続権は孫が持っていたりします。子ども、孫と複数になってくるとより利害関係人は増え、手間は増すばかり…
このようなことを避けるために、地縁団体が不動産に限って、主体となれる様になったのですね。
地縁団体のおさらい
(1)法人格が付与される「地縁による団体」とは?
・ 一般的な自治会活動を行っていること
・ その区域が住民にとって客観的に定められていること
・ その区域に住んでいるだけで構成員になれる団体(構成員は世帯ではなく個人)であること
・ その区域の相当数(一般的には過半数)が構成員になっていること
・ 規約を定めていること(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項)
を満たすことでした。
(2)税金は?
・ 法人税は公共法人扱いとなり、収益事業のみ課税対象となります。
・ 固定資産税、不動産取得税は、多くの自治体では減免の対象になるようです。
(3)性格は?
・ 権利義務の主体となれます。
・ あくまでも住民による任意団体です。
・ 正当な理由がない限り、その区域の住民の加入を拒むことはできません。
・ 認可の前後で檀t内の運営の在り方は変わりません(民主的、自主的、差別なし)。
・ 特定の政党のために利用することはできません。
地縁団体と宗教法人
では、町内にある神社、地域のお祭りの中心となるいわゆる「氏神」さまを地縁団体は所有することができるのでしょうか?
「氏神」さまは、宗教法人となっています。公共法人の扱いをうける地縁団体との関係は?実は、これを確認したくて、備忘録を書いていたのでした。
ここからは、大阪府高槻市のホームページより…
「地縁団体はいわゆる公共団体ではありません。一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であり、宗教活動の禁止や宗教上の組織等に対する支出の制限を定めた憲法上の規定(第20条3項、第89条)との関係は生じることはありません。」
地方自治法上も神社の祠や墓地は地縁団体の保有資産をなりうる、とも記載がありました。
これで、対外的には地縁団体が神社や墓地を所有することには問題がないことが確認できました。
次は、「地縁団体について考える2」で、内部の問題、町費から神社の費用を出すことについて考えてみたいと思います。
防災体験の記~本所防災センター~
2014-04-21 | ブログ
web上の合意形成システムCOLLAGREEで名古屋市総合計画へのコメントをファシリテートする機会が昨年暮れにありました。「安心安全」の窓を担当したのですが、そのときに「本所防災センター」がどなたかのコメントにありました。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hjbskan/honjo-riyou.htm
そのときから、一度行ってみたいと思っていましたが、急に行く機会が訪れました。前日の金曜にTELにて申し込んだところ、ツアーのコースはすでに決まっていましたが、とにかく行ってみることにしました。都市型水害体験(洪水の中でドアを開くという体験。名古屋市にでかけることが増えましたので、是非体験したかったのです)は、あいにく、予約がいっぱいとのことで、断念。これは次回のお楽しみとしておきます。
コースは、
①シアターで映画鑑賞 「3.11で何を経験したのか」というようなタイトルで、東日本大震災時のことをまとめてありました。
②消火器体験 消火器の説明と一人一人が実際に消火器を持って、映像の火をめがけて放水(本当に入っていたのは水でした)をしました。見事、消えたら「消火成功!」の文字がでます。不成功の場合は、めらめらと火が大きくなっていくのです。本当に消火器をさわって火を消すという経験は初めてでした。学校での避難訓練時には体験する場面もありましたが、代表者が一人か二人でて消火するというものでしたので、うれしい体験でした。
③暴風雨体験 雨合羽の上下+長靴を借り、時速20mの風と雨にさらされる体験でした。こちらは、雨がひどく、顔をあげていると洋服まで濡れてしまうので、下を向いて風をやり過ごすことしかできませんでした。実際の台風はもっとひどいような気がしました。ここでは体験も大切ですが、目の前で他人が体験するのを客観的に見たら、とても興味深い気付きがあるような気がしました。
④煙体験 部屋の上半分の空間が煙になってしまい、その下を移動するという体験でした。また、一瞬部屋が真っ暗になり、停電したときの体験もできました。長野の善光寺にある「お戒壇巡り」のようでした。
⑤地震体験 震度7の体験をしました。起こることが分かっていても、動けないものだなと思いました。揺られているときには机の脚にしがみついているだけで精いっぱいでした。
ツアーガイドさんもついてくださり、あっという間の2時間でした。
体験から思うこと
何度体験しても、普段の備えにはなかなかつながらないだろうなぁと思いました。少しずつでも体験後に、防災グッズや非常食などを揃えていけるようにしないと!と思うのですが、帰ってきてしまうと、その気持ちが遠くなってしまいます。もちろん、忘れないように出口には「防災クイズ」もコーナーもあり、おさらいができるようになってはいました。
もう少し違った形で体験をふりかえる、例えば体験の後にHUG(避難所運営ゲーム)を初めて会った人たちとやってみる!というのも良いかもしれません。帰宅困難者という想定にはなりますが。いつも以上に想定外の回答がありそうです。多様性の視点がまた、磨かれますね!
と、そこまではいかなくても、参加した人々で体験ツアーが終わってから、10分でも20分でも感想などを共有する時間をとるだけでもいいのかもしれません。同じ時刻に同じ体験をしたのですから、共有もしやすそうです。実際に、私のツアーには小学生の子どもが3人ほどいましたが、体験中に話しかけたりして、仲良くなりました。その子たちがどんなことを思ったのか、考えたのか、とても興味があるところです。
いずれにしても、せっかくの貴重な体験のあとは、ふりかえり、共有する時間があるといいなぁと思いました。レヴィンの実験にもあるように、しっかりと記憶でき、次の行動につながるのではないかと考えました。提案してみても?


- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
〒444-0838 愛知県岡崎市羽根西2-5-16 TEL:0564-53-0370